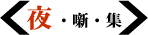序列の逆転
日本の家長制度は、既に完全に崩壊している。金を運ぶ方が文句を言われて、運ばれる方に仕えている。これこそ家が没落していく暗示である。
顔色
人は顔色を観るという行為をする。読むのである。これは、指揮官なれば、部下は常に上官の顔色を読み、全体の未来とともに、自らの未来をも占うものである。戦時ともなれば、舷々相摩するものである。それは烈しい海戦に参加した艦船で、敵弾を受けながらも、こちらも砲撃するようなものである。その最中にも、敵弾がわが艦船を襲い、命中弾を受ける。命中した弾は炸裂する。このとき反射的に水兵は干潮の貌色を観る。
人間の顔は、確かに脳の造りを顕わしているものと言える。脳の造りが顔貌(かおか‐たち)を決定していると言える。しかし、これは形の上においてである。その流動体たる心の動きは、変化が激しく、この顔貌の上に乗って、「今」という表情を顕わして行く。この表情には喜怒哀楽があり、その場その時の一喜一憂がある。顔は、こうした情況に敏感に反応する。
敏感に感応した艦長の貌(かお)には、戦いにおいての意志が表明されているからだ。
艦長がこうした場合、神色自若として敵艦を睨(にら)んでいれば、水兵たちは艦長の貌を見て再び勇気を鼓舞して戦闘態勢に入り自信をもって戦うことが出来る。だが、もし艦長が少しでも怯み、退き下がったような態度をとれば、艦内は混乱に陥り、せっかく勝てる戦いも、負け戦となってしまう。その総ては顔色に顕われるからだ。
表情には、「七情」の七種類の感情が顕われる。素問霊枢では、喜・怒・憂・思・悲・恐・驚を指し、礼記(らいき)の礼運篇では、喜・怒・哀・懼・愛・悪・欲を指し、仏家では、喜・怒・哀・楽・愛・悪・欲を指す。顔に出るのだ。心の動きに敏感に反応するのである。
心配事や不安が心に中に蟠(わだかま)っていれば、憂鬱(ゆううつ)となり、感情が波立てば怒りになり、孤独に浸れば、人恋しさとなって、それが顔に顕われて来る。
古代中国の観相見は、七情などを基盤にして、更にこの上に、顔面を左右130ずつの260に分割し、各々の箇所に顕われる色、表皮上に隠れた筋肉の動き、骨格および肉付などを検討して、そこから観(み)る相手の人柄と運勢を見抜こうとした。
人の顔には、各々に経歴が刻み込まれているものである。しかし、運命を考えるならば、人の顔こそ、人生の総決算を顕わす、決算書ではないかという事がいえよう。人生の結末まで、顔から読み取れるのである。どのような死にからをするか、顔には予(あらかじ)め記されているのである。運命の一切が刻み込まれることになる。
思考する未来
考える人と考えない人。この両者は、今は同じでも、未来はまったく異なったものになっている。
瞑眩反応
病気でも、悲運の只中にあっても、これから抜け出そうとするときは必ず瞑眩(めいげん)反応が起こる。瞑眩とは、立ち眩みなどに似た反応で、善くなろうとするときに必ず起こる悪化状態である。病気は前より重くなり、不幸や不運は次から次へ襲ってくる。しかし、これはその人が感じる幻覚であり、いずれ抜け出して好調を極める。
人生は好調の兆しとして、一見悪化したような瞑眩反応が起こるものである。これを兇(わる)い報せと採(と)ればますます悪くなる。一方良き報せと採れば良き反応が顕われる。
喜怒哀楽の中の人生
愉しみを知る人と愉しみを知らない人の差はなんであろうか。換言すれば日々の生活の中に人間の喜怒哀楽の人生が横たわっているか、いないかを識別できる感性であろう。
現代人の多くは評判や評価を気にしている生活ほど、寂しいものはない。何も気にしないで、人生を愉しんでいる人の表情は生き生きしているものである。
かのドイツの哲学者ニーチェは言うではないか。
「世論とともにそれを考え、気にして生きているような人は、自分の人生の総てに目隠しをして、更には耳栓をしているようなものだ」
一方、フランスの政治家ブリアンは「自らにとって大事なのは、他人が自分のことをどうかんがえているかではなく、自分が彼らのことをどう考えるかだ」と、世間評に対して開き直っている。
人間、評価・評価にこだわるのではなく、逆に評価を切り返す位の度量は欲しいものだ。
当今の世情や労使関係を観るがいい。そこに破滅と墜落の匂いを感じまいか。
経営者が雇用者に迎合したり、急に聞き分けの善いポーズをとるような八方美人的な言動をしたり、政治家が大衆に狐媚(こび)を売るような八方美人的な態度をみせはじめたとき、政治は顛落(てんらく)したり、また企業はやがて倒産の憂き目に遭(あ)ったりするものである。
ふだんの有難さ
人は、悪天候の嵐や暴風雪の泥濘(ぬかるみ)を歩いていると、穏やかな天候の有難さが分かる。同じように、ふだん健康な人が思わぬ事故に遭ったり、大病を患うと、以前健康だったときの有難さが分かる。
時には病気などを罹病して、その中に身を置くと、心の修養にもなるものである。
このことは明代末期の政治家・陸紹こう(りくしょうこう/「こう」という字は「王」遍に、「行」という字を用いるので作字する必要がある)の『酔古堂剣掃』にも出ている。
「人、病中に在(あ)れば、百念、灰の如く冷なり。富貴ありと雖(いえど)も、享(う)けんと欲して不可なり。反(かえ)りて、貧賤にして健なる老を羨(うらや)む。この故に人能(よ)く、無事の時に於(おい)て、常に病の想いを作(いた)さば、一切、名利(みょうり)の心、自然に掃(はら)い去らむ」
健康の有難さを知るのは病気になったときである。
しかし当今の大半の人は、今の健康の中にあっても、どれほど愚行に等しい生活を送っているか、心に手を当てて想い返すべきである。
日々の愉しみ
苦海に等しい憂き世の世界には、大きな倖せなど幾らも転がっていない。そこで、日々の中で小さな倖せを見出し、それを集める。その小さな倖せをたくさん集めると、溜まりに溜って大きな倖せとなる。江戸末期の歌人で国学者の橘曙覧(たちばな‐あけみ)の『独楽吟(どくらくぎん)』には次のようにある。
「楽しみは朝起きいてで昨日まで、無かかりし花の咲けるを観るとき。
楽しみはまれに魚煮て、児等皆がうましうましといいて食うとき。
楽しみは銭なくなりてわびおるに人の来たりて銭くれしとき。
楽しみは木の芽煮やして大きなる饅頭をひとつ頬ばりしとき。
楽しみはつねに好める焼豆腐うま煮立てて食わせけるとき。
楽しみはどぼしきままに人集め、酒飲め、物を食えというとき。
楽しみはいやなる人の来たりしが、ながく居らで帰りけるとき」
ここには何の変哲もない日々の中に、こんなにも愉しみがあるのかと想い致し、日頃の不平不満を論(あげつら)って生きている現代人には、心に安らぎを覚える福音になるであろう。同時に、周囲から評価されないとぼやいている己の生活態度が恥ずかしくなろう。
そして、他人を薙(な)ぎ倒して利益を貪(むさぼ)ると言うことが、いかに危険であるかを思い知らされよう。
企業における労使関係でも、本来は、経営者と雇用者は自他ともに「益」してこそ発展があるのであって啀(いが)み合うことでない。
利益は目的でなく、あくまで結果である。
かの『大学』でいう「徳は本(もと)なり。財は末なり」なのである。
徳とは世の中に役立つことをすることであり、まず徳を示して他人(ひと)に貢献すれば、その度合いに応じて報酬が社会から齎されるのである。それは末にくる利益である。社会への貢献度合いに応じて齎されるものが利益である以上、先に徳を示し、のちに財がくることの順序を把握しておかねばならない。
人物鑑定法
中国哲学の源流に据えられる『呂氏春秋』に人物鑑定法が記されている。その一節に「之を喜ばしめて、以て、その守りを験(ため)す」とあり、これはその人を散々喜ばせて嬉しがらせ、その人はどれほどの守りを備えているのかを検(み)るというものである。もし、その御仁が嬉しくなって有頂天になったり、それを快く思ってにたついたりすれば、その人は当てにならないとし、むしろこういう場合は得意絶頂に陥らず、泰然自若(たいぜん‐じじゃく)として物事に動じないような人物こそ真物(ほんもの)だと言うのである。
第二に「之を怒らしめて、以て、その節を験す」とあり、怒り具合を検(み)るとある。
人の怒りは感情の爆発であるから、怒ればそうとうに心を鍛錬している人でも、日頃の理性を、つい失ってしまう。つまり節度を失うのである。
本来、節とはどんなに怒っても、弛(ゆる)んではならないことであるから、抑えるべきは抑えられることが出来るのが、心の鍛錬の出来た人である。しかし、これはなかなか難しい。セルフコントロールが難しいのである。それだけに、人物評定にはなり易いものである。
第三に「之を哀しまして、以て、その人を験す」とあり、哀しみにはその人の人柄が最もよく顕(あ)われるところである。その人が哀しみに打ち沈んだとき、その心理は露骨になる。
ある人にこういう災難が起こった。娘とその孫を同時に不慮の事故で喪った。当然、親としては血涙を搾るような哀しみだろう。運命を腹立たしく思い、それを怨んだり呪ったりしたくなるだろう。そして、誰が悪いのかといえば誰が悪いのでもない。それだけに、この哀しみを打ちまける相手がいない。誰も責められない。それが、また情けなさを募らせる。一層やりきれなくなって、憤りを投げ付ける対象が無いだけに、想う度に涙が溢れるのである。それはまさに、人間は喜怒哀楽の中に生きているということになる。
第四に「之を楽しましめて、以て、その僻(へき)を験す」とあり、ここには「喜ぶ」と「楽しみ」の違いを浮き彫りにしている。
そもそも「喜ぶ」は人間の本性であって、一方楽しむは、喜ぶに理性が加わる。
その理性の解釈に『論語』の「仁者は山を愛し、智者は水を楽しむ」という一節に行き着く。
山は不動であり、その不動を知る仁者は利害や栄辱(えいじょく)に転ばない。だからこそ、動く水よりも不動として構えている山を愛するのである。
これに対して智者は流転してやまない流動的な水を楽しむのである。流転する世の中を検(み)て、それに誤りなく処していくには、流動する世の中の風(ふう)を読む必要がある。流れを読まねば、顛落の憂き目に遭う。
則(すなわ)ち、喜びは仁者であり、楽しむは智者であって、前者は「愛」と言う本能を顕し、後者は「楽」という理性を顕しているのである。
そこで、人は楽しむと僻という癖(くせ)が出る。その癖は偏りをもつ。これを「偏(へん)する」という。
例えば、酒が好きな人は酒に偏って、最後は酒に溺れる。また女の好きな男は女に偏り、最後は溺れる。美食好きの食道楽ならば、グルメを気取って、美味いものと聞けば何処にでも出掛けていき、行列のできる店に並んだり、世界の果てまでも追い掛けてそれを食べようとする。最後は食道楽から食傷に陥り、躰を壊す。これが「好き」という世界の恐ろしさである。偏るからだ。
その偏りが体躯に顕われると言ってよいであろう。
まずは動く
好運とか儲けのチャンスは、世の誰もが既成概念にこだわっているときである。ゆえに変わり身の速さが思わぬチャンスを掴むことになる。鈍感では、好機を逃すのである。それを誰もが、運が悪いとほざく。しかし運が悪いのではなく目の前にある好運を掴まなかったに過ぎない。この世に時期尚早はあり得ず、石橋を叩いて渡らないのではなく、叩いて渡るより、何事も思い立ったら吉日である。そう感じたら、考える前に行動を起こした方が結果的にはいい場合が多い。
好機を得るにはふだんから未来予測をじっくりと練っておかなければならない。これを疎かにすると、突然にやってきた波に乗れないのである。
静動は表裏の関係
静中の動あり。動中に静あり。何れも表裏一体の関係にある。動は活動する静であり、静は忍耐を必要とする動である。
 |