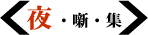建設的意見審議会
国会中継などを観ていると、足の引っぱり合いや揚げ足取りが、やたら鼻に衝く。こういう場合は審議が進まない。会議進行妨害罪などを設けて、甚だしい者は、議長に退場の権限を与えたらどうか。何を喋ってもOKというのは民主主義のルールであろうが、道義や、人としての格のマナーが違反しているのなら、「退場」という権限も有りだろう。
逆に「こうすべきである」とか、「こういう遣り方もある」などの代替案があり、それが良ければ大いに讃え、また可能実行だったり、信憑性のあるものは重視して取り上げ、大いに珍重してこれを讃える。こういう国民側からの議員に対する建設的意見審議会があってもいいのではないか。これを国民審査で遣る。国民審査は全く経歴も分からない最高裁判事を、国民審査で投票するばかりではあるまい。
むしろ議員に対する建設的意見を審議を国民側で、もういちど検討し、一年ごとに国民審査に付され、罷免を可とする投票の方法もあるのではないか。これこそデモクラシーというものだ。
病院の待合室
当今には老人の掃き溜めという場所が増加しているように思う。現代人は痛くなったり、少し変だと思ったら直ぐに病院にいく。我慢できることでも、病院で診て貰う。こうした簡単で短絡的な方法が採(と)られるため、病院の待合室にいくと、そこは老人の社交場になっている。そのダントツは整形外科であろう。この社交場にも、駐車場料金並みに時間制限して有料にしたら、病気でもない老人が、此処を訪れる激減するであろう。
老人医療の優遇制が、斯(か)くもこのようにジジババを甘やかせているのである。これこそ、医療保険の無駄遣いである。
なぜ、このようになったか。
老人の医療負担が安いからである。安いから、湯水の如く遣うというのが戦後の為政者の特徴である。
では、この対策はあるのか。
例えば、一年間、健康に過ごし、日頃の不摂生も慎めば、頻繁に病院通いをしなくていい筈である。そこで、公共機関が負担する医療保険分を一年間全く遣わねば、商品を出すとか、遣わない分、翌年の保険料は割引額が発生するとかすれば、病院の待合室から老人の社交場はなくなるだろう。
かつて北九州市では、一年間全く医療費を遣わねば、その人に対し、高級バスタオルなどのプレゼントがあった。昭和50年代初頭の話である。復活させてはどうか。
自然死体勢を作るためには老人福祉を改める
当今の公的機関の医療費の負担額を検(み)ると、老人医療は優遇し過ぎで、一方若者の健康保険税は高過ぎのように思われる。かつて「人生七十古来稀なり」(徒甫『曲江』の一節)という時代があった。七十年も生きれば、随分と長生きしたと思われていたのである。ところが、当今は七十代、八十代はざらである。多くは過酷な肉体労働から解放され、家庭生活の電化や合理化で、肉体的負担が減ったためであろう。
人生七十古来稀なり……。当今はそんなものは当て嵌まらない。ジジババはみんな長生きである。
そこで、医療費負担も、病気によって年齢制限をして上げてもいいのではないか。
七十代は病気の種類によって4割り負担、八十代は5割り負担。一方、殆ど病気をしない二十代は1割り負担、三十代は2割り負担、四十代は3割り負担というように、老化などによる病気によってはこうした差額をスライドさせて、健康保険税は若者を中心に優遇してはどうかと思うのである。そして、老人の病気によっては、整形や移植に関する医療費は全額実費負担でもいいのではないか。
特に注視すべきは、健康保険は遣えば遣うほど老人に限り、割高にする。こうすると医療費の公的資金の負担金が減るのではないか。そして、老人は老齢期に入ると、自然死の体勢が執(と)れるようになる。死を怕(こわ)がらなくてもいい。
福祉・福祉と、老人ばかりに焦点を当てていると、本当に救わねばならない者が蔑ろにされ、国家財政は出費ばかりが多くなる。国力も弱くなる。再考すべきであろう。
当今は選挙でも、老人に焦点を当てた選挙が展開されている。
斬り伏せる
生死を超越するとは、己の心に勝つ、苦しい修行のことであり、これを乗り越えた時に、達人への道が開ける。則(すなわ)ち達人とは、敵の心気わずかの間断も気を通じて、その隙をすかさず打って勝つもの也。
更に達人に至ると、隙を作らず、敵の刃に触れないで、「斬り伏せる」妙技を見せる。 このことは『兵法心気体覚書』に、そう記載されている。しかし、此処に到達するには日々の地道な鍛錬が必要で、凡夫にはなかなか到達できないものらしい。
問題は、出来ないからと言って、そこで諦めるか、そういうものを度外視して、更に継続するかである。俚諺には、「継続は力なり」とある。
巌の身を動かす剣
『甲陽軍鑑』には「既に据え物を切て、その首の落つるに」とある。一方、武術修行は、精神修行を積み重ねた結果、この時機、会得したものを「奥儀」と呼んで、昔から重視してきた。
剣術では、「剱(けん)の道」の剣として、据え物が単に刀の斬れ味を試すだけではなく、精神高揚の術として研鑽されていく。
また、「巌(いわお)の身」を動かす剣として、心ある武人の礎(いしずえ)になった。そこには「心・技・体」の三者が伴わなければ、不可能であったからだ。
武術修行は、精神修行を積み重ねた結果、この時機、会得したものを「奥儀」と呼んで、昔から重視してきた。この奥儀は、修行を積まない者に伝えても、理解できないから、古人は「免許を与える際」に奥儀を口伝として伝えたものであった。その口伝の中に、剣術は剣術の真髄が横たわっているのである。
炯眼
死相は眼に見えるものではなく、勘の働く第三者が観じるものである。勘の働く異能者は人の生死を観じ、死が近付いている人には、死の人が間近にあることを冷静な感覚で受け止めるからである。常人の見えないところまで見通す……。これを炯眼(けいがん)という。
文武の順の疑問
予(かね)てより文武の順に疑問を感じているのは、決して筆者だけではあるまい。では、なぜ「文」が先に来て、「武」が後に来るのか……。それは、武が勝負にこだわり、殺人剣を振り回し、精神的な屠殺人(とさつにん)を遣っているからである。これは文の連中から最も侮蔑される箇所で、今でも、一等も二等も下に低く視られている。
本来は文と武は両道、そして両方が釣り合っていることを「友文尚武」として尊ばれたのではなかったか。それからすれば、文武は対等であり、同格であるという意味に帰るはずだ。しかし、武が殺伐としていては、屠殺人の殺人剣に成り下がる。武は人を活かすための活人剣でありたい。
文武は、あたかも自他が互いに益するように、文武も互いに益するものでなければならない。
屋台骨の腐敗
刺戟が強過ぎる説教臭い映画でも、小説でも、説教するということにこだわれば、誰も視なくなるし、読まなくなる。大衆はこの手の類は娯楽性を求めているのである。愉しくて、現実逃避が出来、一時の憂さ晴らしに、映画や小説を好むのである。大衆……。
それは民意と解してもよく、その辺に大衆の需(もと)めがあるのかもしれない、しかし、これに頼りすぎれば、威信として屋台骨は腐っていくであろう。時代ごとの変革はその節目に起こるもので、屋台骨が腐ったときに顕われる。
変革……。
大衆は常に変化を求めているのである。変化の少ない中に安定を需めると、やがて所為決まると言う禍(わざわい)が押し寄せるであろう。時々刻々と変化するのは、常に現象界の相対世界でバランスを取ろうとしている働きである。
「ついでに」という二の次
物事の依頼に「ついでに」というのがある。「そこへ行ったついでに……」とか「今度、来るついでに……」というものである。しかし現代人の多くは、自分のことに精一杯であり、他人の依頼事など、二の次である。
二の次を一番に遣れるのは、幕賓(ばくひん)か、側近者だけであり、単に相手が善人と言うだけで依頼しては、二の次は三の次になり、あるいは四の次か、半永久に忘却されて、いつ実行されるか分からなくなる。
これが厭(いや)なら、何事も自分のことは、自分でする自前主義に徹することである。
長い目で観る禍
「長い目で観(み)てやってはどうですか」人は、よくこの言葉を遣って大器晩成を説諭するときがある。しかし、この言葉が中(あた)っていることは稀である。
人を長い目で観てやって、とんだ禍(わざわい)を蒙(こうむ)ることがある。説諭した者に、未来を予見する才がなかった場合は顕著である。
長い目で観てやる人以前に、説諭した人を自身を観るべきではないか。
長い目で観るべき人物は、その人が若年とはいえ、若い時分から、何か一つ秀でた箇所を所持しているからである。才とは、そういうものである。
 |