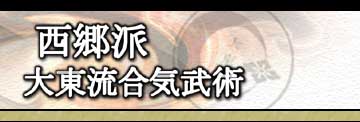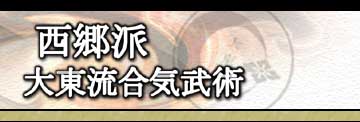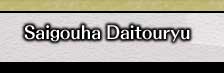■ 大東流 合気二刀剣 ■
(だいとうりゅう あいきにとうけん)
 |
|
著者 曽川和翁
様式 四六判/252ページ
発行日 平成9年4月20日
定価 1,575円(税込)
|
全て完売しました。
●解説(本分より抜粋)
奥義<合気の術>に入っていく為の一つの行法に「合気二刀剣」がある。
この特徴は、単に一対一の剣ではなく、二人以上の一対多数を相手にした「乱」の実戦剣法であり、最終的な「十方之陣」を想定した剣法である。この陣を破ることを「多数の位」、または「多敵の位」という。
二刀剣は、本来同じ長さの剣を左右の手に持って行う「対車の円陣」の技法であるが、必ずしも木剣や真剣を持っていなくてもかまわない。一旦合気が完成し、二刀剣の体捌きと刀法を会得してしまえば、無手無刀の場合でも、自らの手を刀にみたてて行う二刀剣は可能である。
白刃取りは素手で戦う以上、多少の皮膚は切られてしまうことを覚悟しておかねばならない。これを当り前だと割り切れば、これだけで心は気丈になり、刃物を身に受ける恐怖心と切られた際の精神的ショックを幾分にも和らげることが出来る。切られればその箇所によっては出血多量になる場合もある。しかし「転身」すれば敵の切り込みを直角に受けずにすむ。更に付け加えるならば「転換」すれば後退り状態になるが、「転身」すれば「逃げ腰」「及び腰」にならずにすむ。後退りすれば、体重の重心が爪先ではなく、踵に掛るからだ。こうなれば押し捲られて一巻の終りである。刃物は眼で見ても、心で見ないことだ。実戦に於て先入観や固定観念ほど、人の判断を狂わせてしまうものはない。
また白刃取りを行う際、大東流には敵の刃物の構え方で、その熟練度と攻撃方法を予測する《十方之目付》がある。
刃物に対する防禦は一筋縄ではいかない。このことは柔剣道の高段位を取得する警察官が、武道や格闘技の経験のないド素人の容疑者を取り押さえる際に格闘して、簡単に刺し殺されて殉職する事件が度々起こっていることから考えれば頷ける筈である。これは剣道にも柔道にも、柳生流の無刀捕りに匹敵する《白刃取り》の「柔」の術がない為である。 |