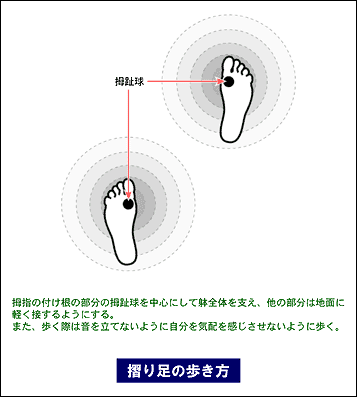松尾君は内弟子として、この日の入門式で、自らの抱負を『声明文』にして、高らかに読み上げた。そして宗家先生より、直々にお言葉を賜り、「心頭没頭して二年間の修行に励んで貰いたい」ことを、激励とともに申し渡された。
また、尚道館・陵武学舍のモットーは、「武門の行動律」を徹底することである。
この武門の行動律と云うのは、威張ったり、夜郎自大になることではない。慎み深く、謙虚に礼節を全うし、「恥辱(ちじょく)に対する感覚」を磨くことである。つまり、誇り高く生きる「名誉意識」を、自身の中に養うことである。
昨今は、若者だけでなく、いい歳をした大人の中にも、恥さらしの人間は多い。他人ばかりを誹謗中傷して、それでいい気になっている恥知らずが多い。
そうした現代にありながら、尚道館・陵武学舍では、かつての先達が恥辱に対する感覚が敏感であったように、また現代社会にあっても、礼儀をわきまえ、自らの襟(えり)を正し、人格の否定にならないように努力する修行に励むのだ。
かつて、サムライたちは、「ひとに笑われる」ことを嫌った。恥辱を受けると云うことを嫌った。恥辱を受けると云うことは、また武士にとって、人格の否定にそのまま繋がり、自らの品位すらも否定されたからだ。
サムライにとって、名誉とは即ち、「命」であり、また「人格」でもあった。その人を表現する「品位」でもあった。その象徴として、サムライ階級は、太刀や脇差を帯刀することが許されていたのではないか。
まず、陵武学舍の内弟子の一員となると、盃(さかずき)の握り方を教わる。これは単に、盃に限ったことだけではない。湯飲み茶碗やコップなどの握り方も同じである。
機能美とともに、現実主義に徹し、「盃は左手で握れ」と教わるのである。
では、なぜ左手で盃を握るのだろうか。あるいは湯飲み茶碗やコップなどまで、左手で握るのだろうか。
武門では、かつて、物を握るのは「左」と定められていた。その理由は、右手と云うのは、殆どのサムライにとって「利(き)き手」であって、もし、右手で握れば利き手を塞(ふさ)がれ、“いざ”と云う時機(とき)に機能しなくなる。そうなれば致命的だ。敗れるか、殺されるかだ。
そうならない為にも、右手は常にフリーハンドにしておくのだ。
物を握ったり持ったりすることで、利き手である右手は制せられれば、咄嗟(とっさ)の時機に、命を失うことになる。つまり、利き手である右手を常にフリーハンドにし、温存させておく必要があるのだ。
これは坐礼をする時も同じである。坐礼の時機も、決して右手を最初には差し出さない。左・右の順に差出し、右手は一番最後になる。大事な右手での反撃が出来なくなれば、修行で培った威力も半減する。
このように内弟子は、「隙のない起居振舞(たちい‐ふるまい)」を、まず最初に教わるのである。
立つ、坐る、歩く、食事をする、入浴する、就寝という日々の日常の中で、いつ、この日常が戦闘状態に入り、「非日常」に変化してもいいように、常時戦場を心掛け、その中に、「我が身を置く」ことを教わるのだ。
※しかし、2010年1月1日に入門式を終え、仮入門期間内の3月28日にまでの、僅か三ヵ月弱で松尾宣弘はリタイアし、今残るのは曽川竜磨ただ一人だけとなった。
曽川竜磨は平成22年2月1日をもって、満一年を終了した。そして松尾宣弘が辞めた3月28日で、1年と56日であり、曽川竜磨一人が、わが流の内弟子の最多継続者となった。
松尾宣弘のように入門式当時、どんなに勇ましいことを宣言しても、結局信念のない、あやふやな、甘い気持ちで、内弟子に参加する者は、最終的にはこうした結末で、尻尾を巻いて逃げるのである。松尾は結局、智慧も、力も、汗も、何も出なかった。
内弟子は、「教えて貰う」という、口を開けて待っている受動型の人間より、自分から積極的に一人稽古に黙々と励み、積極的に先輩の業(わざ)などを盗む、能動型の人間の方が長続きするようだ。それにより、学ぶこと、研究することの面白さも分かるのである。
●追求される機能美
人間の行動律は、機能美に集約されている。
したがって躰(からだ)の崩れ、不用意で不必要な行動、何事かに気を取られ、心がそれに奪われてしまうような愚、集中力の欠けた緊張のない注意散漫の状態を、陵武学舍では、厳しく戒められるのだ。
それは歩き方においても同じである。
廊下の歩き方にしても、階段の上り下りにしても、坐る時にしても、音を立てずに、これらの行動を機能美とともに学ぶのだ。
かつてサムライ達は、跫(あしおと)を立てず歩いた。歩行こそ、日常の動作では、人間が頻繁(ひんぱん)に行う行動の一つである。歩き方にも、用心を重ねるに越したことはない。況(ま)して、「肩で風切るような傲慢(ごうまん)な武張った歩き方」は慎まなければならない。こうした歩き方をすれば、当の本人はいい気になっているかもしれないが、愚かさが目立つだけでなく、人に見られて、心の中では侮蔑されているのだ。
したがって、陵武学舍では歩き方をやかましく言う。
現代人の歩き方は、率直に言えば“なって”いない。デタラメである。敵に自分の居場所が察知されるような無能な歩き方をしている。これでは命が幾らあっても足らないであろう。
敵に自分の居場所を悟られることなく、また、自分の方は敵に近付き、有無も言わさぬ攻撃を仕掛ければならないのである。それくらい、自然に溶け込み、自然と融和し、自然と一体にならなければならないのである。だから、音を立てずに歩くと言うことが、武術家の心構えの基本となる。
武術家として大切な行動原理は「歩き方」である。
人間が歩くと言う行為は、常に大地からの反動を得て、躰を移動させるのであるから、この行動の中には、つまり「歩き方」が会得出来ていなければならず、これが武術家としての「足捌(あしさば)き」となる。
この足捌きは「大地を信頼する」という、日本人の古来からの農耕民族としての畏敬(いけい)の念が示されており、自然の理(ことわり)に適(かな)った「歩き方」をしなければならない。
さて、古来より武士の歩き方は、能や狂言などと同じように、武人特有の「摺(す)り足」であった。
この摺り足の中に、武人の総ての行動原理が包含されていた。
摺り足とは、敵に悟られない歩き方であり、また、自分の居所を知られないようにする歩き方である。
この歩き方は、西欧の狩猟民族の弾むようなステップする歩き方とは異なり、大地を信頼した、農耕民族特有の歩き方である。しかしこうした歩き方は、今日、一部の古流武術などを残し、総べてあとは消失しているようである。
もともと大東流の歩き方は御式内に由来する、殿中作法からも窺(うか)えるように、能や狂言と同じ「摺り足」であった。ところが、昨今の殆どの大東流愛好者は、その重要な基本的な要(かなめ)を忘れ去り、ただ大東流の高級技法ばかりに眼を奪われている観が強い。
大東流の指導者の中にも、御式内と大東流とは全く関係無いものとして、こうした殿中作法である、歩き方を無視する者までいる。
そしてその愛好者の殆どは、競技武道と同じように、ただ相手を負かし、勝てば良いと思って練習しているため、こうした肝腎な行動原理を無視した考え方が否めない。
要するに、今日の武道界を振り返ってみると、柔道や近代剣道の歩き方は、実質的な立場から分析すれば、その殆どが「べた足」であり、既に武人の心構えであった、「摺り足」の基本を忘れてしまっているようである。
また空手や拳法は組手などから窺えるようにボクシングと同じステップを利用した「跳ね足」であり、到底武人の歩き方とは程遠いものがある。
さて、西郷派大東流合気武術は、「歩き」という行動原理の源は、御式内の作法にある通り、能や狂言の摺り足と考えているので、足の拇指(おやゆび)の付け根部分に当たる拇趾球(ぼしきゅう)の膨らみ部を中心軸として、そこで躰(からだ)を支えるように指導している。そして他の部分は地面に軽く接するようにするのである。つまり能や狂言の自然の動きこそ、人間の歩く行動原理だと考えているのである。
拇指の付け根で立脚することこそ、武人の行動原理なのだ。
歩行は、身体の移動だけを目的にするものではない。正しく歩くには、まず姿勢の正しさが大事である。姿勢を正しく保ち、足頸(あしくび)や膝を柔らかくし、体重移動がスムーズに行わなければならない。安易に躰を動揺させず、重心を安定させ、跫を立てないように歩くと云うのが、古来よりサムライの嗜(たしな)みとされた。
また歩行の際、人込みの中でも、人や物に接触したり、物に躓(つまず)いたり、跫を響かせたり、今日の悪しき流行のように、靴の踵(かかと)を踏み付けて摺(ず)て歩く、見苦しい真似はしないものである。
これだけで、現代人の起居振舞(たちい‐ふるまい)は、昔に比べて退化してしまったといえよう。
陵武学舍では、「横柄(おうへい)を慎め」と教える。修行者は、頭を低くして、乞食(こつじき)のような姿勢で、人間は、もっと謙虚になれと教える。
則(すなわ)ち、これこそが武術修行の基本中の基本であり、修行者の身にある者は、不用意な、あるまじき行為や行動を慎まなければならない。
もし、その人が武道家を自称して、横柄であり、傲慢であれば、その人は、不用意と無神経さと、粗雑さを物語るだけでなく、いずれ敵に、飛び道具や刃物で狙われて、我が命を失うことになろう。だから「慎む」必要があるのだ。
つまり、これが隙を作らないと云うことであり、この「隙を作らない」と云うことは、そのまま「敵を作らない」と云う意味でもある。常に、用心をし、行動律に率(そつ)がないように、スムーズに、流れるような機能美を養うのである。これが武門の礼儀であり、また作法である。
そしてこれらを、堅苦しく、見苦しくやるのではなく、流れるような機能美とともに、ごく自然にやるのである。それは決して“かしこまったもの”ではない。また、武張ったものでもない。更には猛々(たけだけ)しいものでもない。
流れる美しさは、武門の礼儀作法の中で、一貫した行動律の特徴を持ち、坐る、立つ、そして歩くと云った動作の中で、前後左右の敵を自在に躱(かわ)し、いつでも対応できるような攻撃態勢を整えるのである。
しかし、こうした日常生活の中に、「日々戦場」の心構えを養い、いつ有事が発生しても、それに対処する能力は現代では忘れ去られ、もともと命を守るものが、スポーツになったり、格闘技になったりして試合場の畳の上、板張りの上、リングの中でしか通用しなくなっている。
こうした現代の悪しき現象は、一連の動作を日常生活から切り離し、それぞれを部分化してしまった為である。そしてこうなると、最早(もはや)反撃できないほど脆(もろ)いものになっている現実に気付かない、現代人の、悪しき日常が出現したのである。
今日の競技武道やスポーツ格闘技や、その他のスポーツ選手の中で、静坐の状態や、中腰の姿勢から、瞬時に跳躍し、抜刀を可能にして、兇刃(きょうじん)の敵の攻撃を躱(かわ)すことが出来る御仁(ごじん)が、果たして何人いるだろうか。
また、機能美の中には「身だしなみ」も入る。服装については簡潔が好ましいが、まず清潔で、質素で、機能的であることが要求される。そしてこれらの条件を満たす為に、「倹約」や「節約」することを学ぶのだ。
つまり、物を粗末にしない。物を生かして遣う。無駄なものを買い入れない。そして、何よりも「さっぱりと片付いている」ことが好ましい。
そうした機能美を、礼儀・作法の中から学んで行くのである。
●内弟子として入門を許されたからには
陵武学舍の内弟子は、師匠のお膝元に一緒に居ることを許され、家事一切をこなしながら、「薪水(しんすい)の労を取る」のである。その上、学び、鍛練し、文武両道を目指す。そしてそのカリキュラムは、流れる歳月とともに、自らを向上の軌道の上に乗せて行くのだ。
大方の目安は次の通りである。
此処では、全修行の2年間の行程を、まず「前期」と「後期」に分け、第1区分から第6区分に分割し、各セクションごとに習得・修練して行く。
|
内 弟 子 修 行 2 年 間 の カ リ キ ュ ラ ム の 全 貌
|
|
第1年次
(前期)
|
第1区分
なれる
(3ヵ月)
|
内弟子修行の入門が許されて3ヵ月未満……見習い門人として扱われ、儀法を行う為の基礎体力の養成、基本動作や起居振舞(たちい‐ふるまい)、言葉遣い、礼儀作法、畑作業、剣術の素振り、見取り稽古、合気揚げ鍛錬など。
|
|
第2区分
さわる
(4ヵ月)
|
入門が3ヵ月から半年未満……本稽古が許可され、一般門人に交じっての稽古が許される。つまり、3ヵ月を経て、はじめて「正式門人」となる。また武道具などに「さわる」ことが許される。
基本業(剣術ならびに柔術、腕節棍の基本)や山稽古、基本馬術や滝行、呼吸法や静坐法。また整体術指導や、日常の作業として買い物や料理法などを指導。 |
|
第3区分
まねる
(5ヵ月)
|
半年から1年次終了時……これまでの稽古を通じて、諸先輩の技術を「まねる」のである。
剣術・柔術・抜刀術・試刀術・陶物斬り・居合術・居掛之術・腕節棍・杖術・棒術・槍術・手裏剣術・飛礫術・弓術・馬術・その他の行法など。以上は初伝から中伝のもの。刀剣鑑定の基礎など。 |
|
第2年次
(後期)
|
第4区分
まなぶ
(4ヵ月)
|
入門後1年以上……実践を中心にしたテーマに取り組む。「まねる」ことを知り、次に“まねる”ことから「まなぶ」ことを教わる。
技術的な専門分野(口伝による秘術など)も加味しながら、道場経営やそのマーケティングの調査・ 経理ならびに『貸借対照表』の読み方・組織作り・講話などの話術・企画力や指導力の養成・HPを通じた門人募集や制作など。
|
|
第5区分
考える
(4ヵ月)
|
専門技術を学びながら、刀剣鑑定の眼利き技術や古物商許可申請などを行う。第2年次の半ばに差し掛かると、これから先の「人生の計」を考えるのだ。陵武学舍で奨励しているのは、「古物商」である。(都道府県公安委員会許可の「古物商許可証」の取得までを指導)
更には将来、「刀剣商」や「美術品商」としての生計の道も開く。人脈を上層階級に繋ぐ為でもある。風流を解し、美術鑑賞などの美意識も養う。
武術家は単に強弱論に固執して、若い時期の“一時的な勝ち”を求めて奔走してはならない。人生を生き抜く為に、理財の才を養い、ある程度、リッチでなければならない。日々の暮らしに困窮しては、折角、身に付けた技も無に帰するだろう。 |
|
第6区分
卒業する
(4ヵ月)
|
卒業を控えて3ヵ月目には『卒業に際しての課題』が課せられ、“2年間の修行の成果”が試される。この卒業テーマに合格して、あえて卒業ということになる。 |