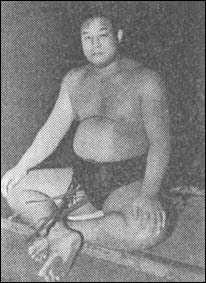| ●どこで何を学んだかは問題ではない 曽川宗家は兼ねがね、武術や武道というものは、体格や体力に優れ、素質があり、伎倆(ぎりょう)が人より勝り、運動神経が発達していて、勝負強い者達のエリートのものであってはならないと口にされる。この門扉は何人も、同等に開かれているという。 真摯(しんし)に武術を志す環境は、実は大衆の為にあり、この大衆が形成されて、これを以て日本独特の「尚武の民」になるべきだという発想を抱いておられる。 また武士道精神はエリートだけが実践するのではなく、むしろ大衆の中からその実践者が出て来て、それが国民的に普及するべきだという思想を持っておられる。この結果、日本は「尚武の国」になりうると言うのである。そして、その国の民は「尚武の民」である。 ここに無形のものに敬意を払う実態がある。 昔、私が聞いた話である。 ある薬問屋の老舗に勤めていた丁稚(でっち)二人が、店が潰れて閉店される間際、店の主人から呼ばれて、こう言われた。 「店を閉じるにあたり、他の者(番頭や手代)には各々に補償して、私の知人の店に勤めて貰う事にした。しかしお前達は気の毒だが、どこにも雇ってくれる店がなかった。そこで、これは私が内緒でコツコツと溜めた隠し金150万円(今で言う1000万円弱であろうか)がある。また、今まで先祖から引き継いだ薬(軟膏/なんこう))の造り方の記した秘伝書がある。この各々を、お前達に渡そうと思うが、さて、お前達はこの金と秘伝書のどちらをとるか?」と訊ねられた。 一人は「金の方が有難い」と言って150万円を選んだ。もう一人は、「金には一銭にもならない、その変わりに薬の造り方を記した秘伝書が欲しい」と申し出た。 さて、この二人の以降の人生はどう変わったのであろうか。 一人の丁稚は、今まで持ち慣れぬ大金を手にした為、一時の有頂天で使い果たして身を窶(やつ)し、苦海に身を沈めた。 もう一人は、秘伝書を元に苦労しながら研究を重ね、ついに優れた軟膏を造り出した。そして後者は、小さな薬屋を開業した。最初は一人ではじめた薬屋であったが、軟膏の効き目が評判になり、従業員も次第に増え、今では大製薬会社にまで成長して、何万人のという社員を抱える程の初代社長を勤めた。 この話は、大阪では知り人ぞ知る逸話となって、現代でも語り継がれているが、ふと、この話と曽川宗家の「内弟子制度」が、どこか重なっているように見えるのだ。 ここに実学の、本当の威力があるのではあるまいか。 世の多くの格闘技やスポーツ武道の愛好者は、とにかく肉体を酷使して体力造りに励み、肉体信奉者としてその道を直疾(ひたはし)る。ところが歳をとり、初老に差し掛かる頃には、体力も衰え始め、肉体力はどんどん低下する。昔ならした凄腕の伎倆(ぎりょう)は見る影もなく、老いぼれの年寄りと化しているのだ。 このざまは、公園や空き地でゲートボールを楽しむ老人以下の姿と成り下がる。もはや死を待つだけの、哀れな姿と言ってよい。
幼い頃事故に遭い、右眼が失明に近い状態になった事は、往年(おおねん)の相撲ファンであれば誰でも知っている事であろう。しかし彼は、そのハンディキャップを乗り越えて、相手の力士の動きを視力に頼らず、一瞬の気合いと勘で、完璧な「強さ」をものにした力士である。 ところが歳をとるに従って、六十九連勝の記録を作り上げたにもかかわらず、彼の前には新たな恐怖が次から次へと襲いかかった。体力全盛の若い頃ならいざ知らず、四十の声が近づくと、その立ちはだかる相手は、個々の力士ではなく、白い死神のようなものが押し寄せ始めた。 これは巌流島で佐々木小次郎と闘った、それ以降の宮本武蔵の心境に酷似するだろう。強者には、極度の緊張が強いられるものなのである。いつ敗れるか、いつ敗れるかの脅迫観念だ。 双葉山の晩年は疑心暗鬼に陥り、横綱を張った若い頃とは打って変わって惨めなものであった。 そして不安の出口を求めて、東京と太宰府に相撲道場を創設する。またこれが、日本の敗戦間もない頃で、耳目を驚かせる璽光尊(じこうそん)への帰依と繋がり、世間をあッと言わせるような事を引き起こす。 このスキャンダルは、囲碁界の天才児として、同じ懊悩(おくのう/行き詰まり)に直面していた、呉清源の口車に乗せられて、現人神を名乗る狡猾な中年女性が教祖を勤める教団に馳せ参じた挙句、この教団の手入れに当たっていた警察官と大乱闘を働き、公務執行妨害と暴行障害罪の容疑で御用となり、一夜の留置とあいなった。 一夜明けて釈放となったが、「自分は悲しいかな、学問がなかった。あの宗教の中に、己を導く何かがあるのでは、と深入りしているうちに、ああいう結果になってしまった」と、寂しく語っただけであった。 宮本武蔵は十三歳から二十九歳迄の間に、六十数回の試合に勝ったが、三十を過ぎるとピタリと試合をやめ、剣を筆に握り変えて、書に打ち込み、水墨画に打ち込んだ。そしてこの世界でも名人の域に達し、諸国を放浪した後、晩年は熊本に流れて、禅僧を、おのが師と仰ぎつつ、そのかたわら、『五輪書』を著わした。 私が感ずるに、もし双葉山に教養があり、少しでも学識があったならば、恐らく武蔵のような晩年を送る事も可能であっただろう。 武蔵の著わした「地・水・火・風・空」の五行は、宇宙の根源のエレメントであり、これと己が一体になり、無心の強さに辿り着くとされている。 もし双葉山にも、教養があり、学識が合ったならば、こうした武蔵の名著の並ぶ、晩年の新たな業績を残したかも知れない。 曽川宗家が、兼ねがね力説する「友文尚武」の教えは、実はこれを明確に顕わしているのであろうと思う。 ●陽明学と「まごころ」 曽川宗家の教えの根本は「まごころ」である。 「まごころ」は陽明学で言う「まこと」であり、この「誠」を以て、人に接し、「誠」を以て人を導くというのが人間教育の根本になければならない。曽川宗家はそう断言する。 だから「内弟子制度」の門を叩き、入門が許されれば、その時点で入門許可を受けた門生は、心と心をぶつけ合う、人間教育に足を踏み入れる事になる。何事も、真摯に受け止め、それを実行し、展開する、その努力を要求される。 それは技術面だけに止まらず、精神面あるいは霊的な面の向上まで要求されるのである。 では、陽明学で言う「まごころ」、つまり「まこと」とは何か。 これは松下村塾の創始者・吉田松陰の教えに回帰する。 物事を学び、それを消化し、あるいは身に着けていく為には、一方的な、今日の小・中学校ならびに高校や大学で行われている、一斉授業方式ではダメである。 教える側の一方通行では、効果が半減するばかりでなく、落ちこぼれるという弊害すらあるのだ。 曽川宗家の指導は、こうした事を非常に嫌う。 それは人間と人間の心の触れ合いを感じないからだ。 つまり「まごころ」に回帰し、誠を以て人を諭(さと)していくものでなければならないと考えているからである。 したがってこの接点は、「真剣勝負」であり、おのが心の、誠意が相手に伝わらぬような、口に変化の見られない腹話術では、意味が無いと曽川宗家は言う。 さて吉田松陰は、人間教育をその一方で、殉国(じゅんこく)教育と題していた。この殉国教育こそ、その原点は「武士道」であり、それは松陰の『南進論』などに見られる。 またこれは、後の「大東亜共栄圏思想」の論拠になるものであった。しかしこの思想は戦前・戦中、軍国主義鼓舞の為に、一部の軍閥に用いられ、侵略思想だと罵声を浴びたが、実はそう言うものではなかった。 松陰は亡国を危惧し、その実態は憂国(ゆうこく)の士であった。 「近時、ヨーロッパ列強が東洋を侵略しつつある。まずインドがその毒を被り、つづいて清国がその辱(はずかしめ)を受けた。余焔(よえん)はまだおさまっていない。琉球を窺い、更に長崎に近づいた。天下の人士はひどく心を痛めている。防禦の策を講ずることが急務ではあるまいか」 これは阿片戦争(【註】1840〜42年、清朝の阿片禁輸措置からイギリスと清国との間に起った戦争)が勃発した当時の、松陰の気持ちを顕わしている。ヨーロッパ列強の、東洋侵略を危惧したのである。 曽川宗家の教えを紐解くと、ヨーロッパの帝国主義・植民地主義は、十六世紀の大航海時代に幕を明け、ヨーロッパ植民地主義の侵略の矛先は「東洋」であった。 そして十九世紀の阿片戦争まで飽くことがなかった。松陰は、そんな時代に生きた人だと言う。 しかし松陰の生きた時代と、今日は、非常に酷似すると言うのだ。 だから、松陰の生き態(ざま)を現代に照射する事こそ、これが「建学の綱領」にかなっていなければならないと言う。 つまり曽川宗家の教えの根底には、単に横文字文化に流される事なく、自分の足許(あしもと)をしっかりと瞶め、弱肉強食主義で、弱い方が疎外されつつある現代、こうした現象を憂い、金銭至上主義を重視して、働く事を嫌う享楽的な風潮が瀰漫(びまん)する今日の世の中を嘆き、心を痛めている葛藤がある。 では日本人が日本人らしく、毅然(きぜん)と振る舞うにはどうすればよいか。 この凝縮されたものが、今、曽川宗家が考えている「内弟子制度」の根底に流れているのである。 つまりこの制度を要約するならば、「現代の松下村塾」であり、「現代に生きる武士道集団」の育成という事が言えるであろう。 そして「建学の綱領」の根本を成すものが、つまり曽川宗家が力説する「実学」だ。 この実学こそ、陽明学で言う「知行合一(ちこう‐ごういつ)」であり、「知っている事と、行っている事は同じこと」という意味のものである。 これは吉田松陰の『西游日記』に端を発している。 松陰は「旅」こそ、人生においては「重要」な意味を持つと考えていたのである。この重要性が、また「旅の哲学」となっている。 さて、諸氏は「旅」と「旅行」の違いをご存じだろうか。 旅は「人生」にも例えられ、そこには人が踏むべき道標の路標が立っているが、これを一々見聞し、それの自分自身に取り込んで、人との出会いを重要視するものである。 ところが旅行は、豪華な交通機関の座席を利用して、物見遊山の限りを尽くして、温泉に浸かり、美食に舌鼓を打ち、世間の見聞もそっちのけで、贅の限りを満喫するというのが、これだ。 この意味で、両者は全く正反対の意味をもっている。 松陰の『西游日記』は貪婪(どんらん)なまでの見聞と、多感な好奇心で満ち溢れている。 そして松陰は言う。 「道を学び、自分を完成するためには、古今の歴史や世の中のことを知らなければならないが、それは一室に閉じ篭(こも)って、本を読めばいいというものではない。また旅などに、出る必要もないと考えている者が多い。しかし私はそうは思わない。 心というものは生きている。生きているものには必ず『機』というものがある。『機』は物事に接触するにつれ、輝きを発し、感動する場面に遭遇する。 この発動を促してくれるのが、つまり『旅』だ」と。 松陰は人間の心の活性化を求めて旅をしているのである。 では、心の活性化とは何か。 それは陽明学で言う「誠」であり、「まごころ」だ。「まごころ」で接する時にのみ、人は真価を発揮しえるものなのだ。 松陰は、誠を尽くして、それに感じない者はいないという。この信念で、松陰は死ぬまでこれを貫き通す。その誠を求めての旅立ちが、松陰にとっては『西游日記』だったのである。 そしてこの旅は、山鹿流兵法の祖・山鹿素行の伝承の地、平戸(長崎県平戸市)であった。 平戸は長崎県北部の城下町で、平戸島と度島(たくしま)を市域とする松浦氏五万六千石の水産業の街であった。古くはポルトガル人が渡来し、江戸時代初期にはポルトガルをイギリスと通商が行われ、オランダ商館が設けられた城下町だ。 そして平戸藩は、心形刀流(【註】伊庭英明是水軒(いば‐ひであき‐ぜすいけん)が流祖。二刀乱斜刀を特異とする剣術流派)の達人で『甲子夜話』の著者で有名な第三十四代藩主・松浦壱岐守源清こと、松浦静山(まつうら‐せいざん)の誉(ほまれ)高き事で知られる。 松陰が平戸を訪ねた時、当時の平戸藩家老は葉山左内(さない)であった。左内は号を「鎧軒(がいけん)」と言い、陽明学の佐藤一齋(いっさい)に学び、山鹿流兵法と共に陽明学を修めた人物であった。 松陰は葉山左内の事を知ったのは、下関(山口県下関市)で廻船問屋(かいせんどんや)を経営する大年寄の伊藤家の当主・木工之助から、「平戸藩には家老の葉山鎧軒がいる。鎧軒は海外事情にも詳しく、九州きっての蔵書家でもある」と聞かされた事から、九州遊学を決意させたのだった。 葉山左内は大坂(おおさか)の平戸藩邸の重任である時、「大塩平八郎の乱」が起こった。 当時の大坂の街は騒然となり、この乱に乗じて、火付けや強盗事件が相次いだ。その時、左内は藩邸を護り、また、天保の飢饉でも、藩勘定奉行として飢饉救恤(ききん‐きゅうじゅつ)に大きな功績を残した人物であった。 参勤交代で藩主について江戸に赴いた時も、以降江戸に出る度に、いろいろな書物を買い求め、その書籍は儒学だけに止まらず、欧米海外事情に通じた洋書にまで至ったという。 こんな時、好奇心旺盛な松陰が彼を見逃す筈がなかった。そして左内の海外通が、松陰に「海防論」を論ずるに至らせるのである。 こう言う意味で、松陰にとって、西国への旅は、まさに人との出会いであり、「まごころ」の示し時機(どき)であった。 そして松陰は、阿片戦争当時の先進国ヨーロッパ列強の弱肉強食の理論を、まざまざと見せつけられる。 以上の内容については、曽川和翁著『大東流合気二刀剣』(愛隆堂)に詳しく出ているので、是非ご一読を御薦めする。 また、松陰は中国の中華思想に対して、このように論じている。 「自国を『中華』と称して、その取り巻きを東夷(とうい/黄河の中・下流地方の東方に住む異民族)、西戎(せいじゅう/青海付近・黄河の源流域から甘粛省東部にわたる地域に居住したチベット系ないしトルコ系の諸民族)、南蛮(なんばん/インドシナをはじめとする南海の諸国)、北狄(ほくてき/北方塞外の匈奴(きようど)・鮮卑(せんぴ)・柔然(じゆうぜん)・突厥(とつけつ)・契丹(きつたん)・ウイグル・蒙古などの遊牧民族)というように、異民族を卑しむ事は、中国人の古い考え方だ。 しかし中国人が夷狄(いてき)を軽視するのは人種差別ではなく、文化程度の低いものへの対し方だという事は注目すべきだろう。春秋時代の楚(そ)が、はじめて夷狄扱いされながら、やがて文化水準を高めるにつれてその蔑称が消滅した事実もある」と言う内容を、「中国・夷狄の論、浅見氏(浅見絅斎(けいさい)/江戸中期の儒学者で、名は安正。通称、重次郎。別号、望楠軒。近江の人で、山崎闇斎(あんざい)に学び、崎門(きもん)三傑の一人と言われる。気節を尚び、尊王説を唱えた)と同じ。ひそかに亦(また)敬服す」と評語しているのである。 今日の多く日本人は、欧米先進国に対する卑屈な迎合の姿勢を崩さないのは、明治維新以来の、現代にまで続く、我が国の国民気質が「欧米崇拝」によって齎されているからである。 世に学者と言われる人は多い。 しかし彼等の多くは「知行合一」を知らない。 だから曽川宗家は、「教養を高めても、学者になってはいかん」と言う。「実行が第一」だと言う。 「書物に書かれている事を知っているだけでは役に立たない。それを心がけ、それを実務として実行すれば、即知っている事が行うことであり、その行いの中から知恵が生まれるものだ」とも言う。 ここに曽川宗家の「実学主義」があり、陽明学の「知行合一」の原点があるのだ。 こうした実学主義の探究も、その根源を求めれば、松陰の、「犬死」を避けた「不朽の見込み」に回帰され、それは死生観までもを網羅(もうら)しているのである。 ●松下村塾時代の松陰と高杉晋作の会話 ある時、高杉晋作(しんさく/久坂玄瑞とともに松下村塾の双璧で、松陰の愛弟子。奇兵隊を組織した事で知られる。慶応二年(1866)長州再征の幕府軍を潰敗させた。1839〜1867)は松陰に、こう訊ねた。 「先生、男子はどこで死ぬべきですか?」 これについて松陰は即答できなかった。 しかし松陰が獄に繋がれ、処刑が直前に迫った頃、松陰はこれに確答を出せる機会に恵まれた。 高杉は松陰に手紙を送った。そして死を目前に控え、そこで悟りえたのは人間というものの「死生観」への悟りにも似たものだった。 松陰は、高杉の問いに答えて、返事を書く。 「死は怖れるものではなく、また、憎むものでもない。生きて大業をなす見込みがあればいつまでも生きていたら宜しかろう。死して不朽の見込みがあると思うのなら、いつどこで死んでもよい。要するに死を度外視して、なすべきかが大事なのだ」と。 高杉はこれまで「潔く死ぬ」事ばかりを考えていた。 潔く死ぬ事が武士の美学だと信じ切っていた。逃げる事を恥辱と思い、辱められる事を死以上の屈辱と考えていた。 ところが「大業をなす見込み」の点において、成就するまで「いつまでも生る」事を選択した。したがって幕府の官憲に追われると、高杉は「能く」逃げたのである。 その逃げ足の早さと、忽然として姿を顕(あわ)わす態(さま)は「神出鬼没」と揶揄(やゆ)された。この意味で高杉は、「犬死」を避け、「不朽の見込み」のある死場所を探していたとも言えた。 師の志しを受け継ぎ、その行動原理の根本を支えたのは、松陰の発した「大業をなす見込み」であり、やがてこれが「死して不朽の見込み」ありとして、西洋式練兵を基盤とした奇兵隊を組織するまでに至るのである。 そして松陰の一言は、死を目前にしながらも、その愛弟子(まなでし)・高杉晋作に挙兵の敢行を促し、愛弟子を通じて、歴史の流れを旋回させたとも言えるのである。 ●「瑞穂の国・日本」の四季の思想 日本の自然には「四季」が存在する。 これが春・夏・秋・冬である。 また人間にも、これを同じ「四期」がある。 これが生・老・病・死である。 松陰は人間の四期を、大自然の四季に準(なぞら)えている。 彼の死生観を語った『留魂録』第八章には、「今日死を決するの安心は四時(四季)の順環(循環)に於て得る所あり」とあり、穀物の収穫に、それを例えている。 つまり要約すれば、「今日、死を覚悟した私は、私の心を成す平安の訪れは、大自然の四季、春・夏・秋・冬を順に経験し、その季節の移り変わる事によって、既に終着点に達し得たものだと感得する次第である」とでも、訳せようか。 松陰は言う。 「農事を見るにつけ、春に種を蒔き、夏に苗を植え、秋にそれを刈り取り、冬に収穫した穀物を貯蔵する。『冬』の『ふゆ』は、一方で「殖(ふ)ゆ」である。秋に至れば収穫しそれを祝って酒を造り、甘酒を造って農村は歓喜に満ち溢れる。 今、私は今年で三十歳になった。ところが一事の成功も見る事なく、死を迎えようとしている。 これは穀物に花を付けず、実らないままの状態に似ている。何とも口惜しい限りだ。 しかし私個人の身の上について言うならば、今が、花を咲かせ、結実した時機に他ならない。 何を悲しむ必要があろうか。 何故ならば、人間には寿命(【註】現世での生存の年月の長さ)というものが定まっていず、人各々なのだ。そして穀物のように必ず四季を巡らねばならないというものでもない。 十歳で死に逝くものは、おのずと十歳においての四季があり、二十歳で死に逝くものは二十歳の四季が、三十歳で死に逝くものは三十歳の四季が、そして四十、五十、百と、各々の齢(よわい)に応じても、各々に四季が存在するのだ。 十歳で死ぬのが短過ぎるというのは、茅蜩(ひぐらし/夏から秋にかけ、夜明けや日暮に、高く美しい声で「かなかな」と鳴くセミの事で、その寿命は一週間ほど)をして長生の樹木たる霊椿(れいちん/長寿を得た椿)たらしめんとするようなものであり、また、百歳をもって長寿と見るのは霊椿をして、茅蜩たらしめんとするに似ており、孰(いず)れも天から与えられた寿命に達したとは言えぬものである」 これは例えば、千年杉が八百年で枯れて死ねば、早死であり、一日の命しか持たぬ熱陽炎が、一日の満期を得て死ねばそれは長寿というべきである。したがって、一概に寿命というが、それは時間的な長短をそれに準(なぞら)える事ではない。 そして松陰は、こうも言う。 「私は今、三十歳。そしてこの年齢をして四季が備わっている。花も咲き、三十歳としての結実も果たした。ただ、その結実後の実が単なるモミガラなのか、粟(【註】アワの意味であるが、本来はイエス・キリストの「一粒の麦」に例えたのであろう)であるかは、私の知るところではない」 松陰は獄中にあり、刻々と死の時刻が近づく我が身を顧みながら、死との対決を繰り返した後に導き出した貴重な言葉である。 今も昔も変わりないが、囚人の多く、特に死刑囚の多くは、生を断ち切られる恐怖から逃れる為に、宗教に帰依する者は多いと聞く。宗教に帰依する事によってのみ、その死の苦しみの恐怖を和らげ、死に逝く自分を、少しでも美化しようとする。この美化意識は、念仏宗の「南無阿弥陀仏」のそれにも酷似している。死して、阿弥陀如来の膝許(ひざもと)に行く。しかしこれは幻想に過ぎない。真諦(【註】宇宙の玄理)ではなく、俗諦(真宗や浄土真宗の念仏宗を布教する為に方便)の戯言(たわごと)だ。 ところが松陰は、神仏にそれを求めなかった。ひたすら知性と、闘魂の意志力によって、死を克服しようと努めた。その闘魂を著わしたのが『留魂録』である。 そして松陰は、ついに死生観を超越し、悟りに至るのである。 松陰が死に際、言い残した「結実後の実が、単なるモミガラなのか、粟であるかは、私の知るところではない」の結びは、三十歳で結実した実は、決してモミガラなどではなく、見事な「一粒の麦」であった事は、歴史が証明しているところである。 徳川幕府は、松陰を殉教者たらしめんとして、自ら墓穴を掘り、世の中は倒幕運動に向かって回転し始めるのである。 古今東西の専制政治は、常に、こうした末路を辿るものなのである。この意味で松陰の刑死は、明治維新の転機となりえた事は明白な事実で、彼自身の先駆者的な行動は、その総てが、陽明学の言う「まごころ」で、「知行合一」に裏付けされていたものであるという事が分かる。 ●尚道館の「内弟子制度」の狙い 何人も、人間である限り、「等しく、同等同格に評価されねばならない」というのが曽川宗家の考え方であり、人間は、平等である前に「同格でなければならない」というのが、また、宗家のお考えである。 民主主義における「自由・平等・博愛」の精神は、互いに矛盾し合う要素を含んでいる。 特に、自由を優先すれば平等が崩れ、平等を表すれば、博愛が成り立たなくなる。本来、人間が平等に人類を愛する、民族を愛する、人種を愛するという事は実行不可能で、人類はそこまで進化していないのである。 もし博愛の名を以て、博愛主義を優先すれば、まさに自由は、その威力を失ってしまう。 こうした事を洞察すれば、矛盾の禍根の中に、民主主義が鎮座している事は一目瞭然であろう。そして由々しき、忌まわしいものの一つに「多数決・決議」があり、これは人民が愚民であればある程、愚昧化政策を行いやすく、「悪の多数決」になる事は、多くの諸氏も、お気付きの事であろう。 人民への集団催眠術、そして国民が「愚民」であれば、民主主義は即「悪魔の道具」となりうるのである。 |