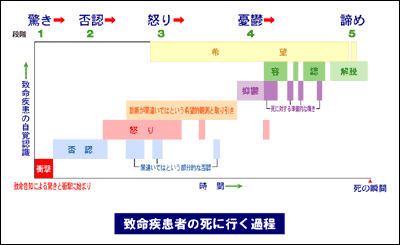会員の声と相談者の質問回答集19
|
末期ガン患者と、どう付き合えばよいか (34歳 主婦 会員)
|
回 答
| 人は生まれた以上、その後に残るものは、死を待つばかりの人生となる。これはどんなに否定しても、覆(くつがえ)すことの出来ない事実である。したがって、人間は生きている間に、如何に「生死を解決するか」という事が問題になる。 生まれて死ぬ。これは人間に最初から定められた宿命である。しかし、生まれて、死んで行く迄の間に、人は、自分の全うすべき人生を全うし、「生まれて来た」ことに値する使命を果たすのである。その使命には「生死を如何に解決するか」ということも含まれよう。 しかし一方で、突然に襲って来た死し、生死を解決できずに、悲愴(ひそう)な気持ちを味わいつつ、死んで行く人は多い。こうした「悲しみ」で、死を迎える人は意外に多いのである。そして、死に行く人にとっては、この悲しみが、やがて「迷い」となって、成仏の妨げとなる妄執(もうしゅう)を招き寄せるのである。これが仏道で云う「迷妄(めいもう)の執念」である。 さて現代人は、その多くが、病院で生まれ、病院で死んで行く。こうした死んで行く人の多くは、かつての日本人が、月の「満ち欠け」によって、生まれ、死んでいった事と、逆行する運命を辿っている。月は太古より、潮汐(ちょうせき)を通して、人の死に関わっていた。 しかし、今日では現代人が病院で生まれ、病院で死んで行く現実を見れば、人が自然死で、汐(しお)が引いていくように、死んで行くことは殆ど考えられない時代になった。この意味で、現代人は、古代人より退化した文明の申し児と言えよう。そして「退化」の実情の中で、現代人の生と死が繰り返されているのである。 その為に、現代人は、「人間が死んで行く」という現実を充分に学習する時間がなくなっている。つまり、「人の死とは何か」ということに、赤の他人の不幸を見るような眼で見ているのである。 「人の死」というものが、よく分からない為に、「物事に始めがあり、終わりがある」という「けじめ」の大切さを知らないのである。 「けじめ」を理解しない人は、その生涯において、常に迷いっぱなしで人生を送り、生死を解決できないで死んで行く人である。 安易に「人の死」と云うが、生死を解決できないで生涯を終える人は、「人間のけじめ」をつけることができないので、再び六道(りくどう)を輪廻(りんね)して、「迷い」を繰り返す事になる。六道を輪廻する事を繰り返せば、これこそ「終りなき生き方」と言えよう。 死を最後のものとすることが出来ず、再び「生の世界」に生まれて、「迷い」を繰り返すのである。こうした「終りなき生き方」は、その人にとって、むしろ残酷な「生」であろう。 要するに、「死ねない生き方」を繰り返すのである。これは「永遠の暗い死」に匹敵しよう。 現代では、こうした「けじめ」の付けられない生き方をする人は多い。特に、現代病の第一位にランクされる末期ガンで死んで行く人などは、「死ねない生き方」を選択する人が多い。死ねないから、次の「生」への新たな循環がなく、永遠に死ねない「生」へと迷いを募らせる。これが不成仏の実体だ。 末期患者の特長は、最初、自分が「ガンである」ということ否認する。それはガンが完治しない「死病」と思い込んでいるからだ。自分がガンであると云う事は、「もう直(じき)死んで行く人間」ということを認めなければならないからだ。 しかし、数週間が経ち、落ち着いた頃、遂に否定できなくなり、主治医のすすめで、二度三度と手術を行い、あるいは入院加療を受けて、「生への延命」を試みる。しかし、その後の容態は以前にも増して芳(かんば)しくないことを知る。手術を受けても、あるいは延命効果のあると言われる、ガン疾患に有効な種々の療法を受けても、その後の華々しい決定的な治療の効果の痕跡(こんせき)は殆ど顕われないからだ。 そればかりか、無理な治療が加わった為に、幾つかの併合した合併症が顕われ、体力は衰弱し、延命に賭(か)けた期待は、一層大きく裏切られる。その時のショックは、計り知れないものであろう。それは多額な治療費を注ぎ込んだ上での「延命効果」を期待しての、裏切りであるからだ。 しかし、多くはこうした形の治療を受け、ついには集中治療と入院には、莫大(ばくだい)な数字に上り、多くの患者はその人が老後の生活プランとして蓄えた、唯一の持ち物すら手放さなければならなくなる。老後の為に建てた家屋も、もはや維持できなくなるだろう。 そして若い頃に夢見た、晩年の人生のラスト・スパートの悠々自適(ゆうゆうじてき)の生活の夢は、実現不可能に帰するであろう。そうしたものへの執着と、死んでいかなければならない怒りとが、ごちゃ混ぜになって、末期患者の顔つきには憤怒の表情が顕われるのである。 さて、死病を抱えた末期患者の多くは、次ぎのような「死に行く過程」を経験して、死に就(つ)く事になる。
末期患者は、自身の抱える病気が、もはや現代医学の治療法で癒(なお)らない事を知る。あるいは手後れであった事を知る。 |
|
ガン予防の為の断食の効果は (50歳 主婦 会員)
|
回 答
| 現在の日本に於いて、ガンを筆頭に、様々な生活習慣病は急増するばかりで、世界の中でも医療の発達したと自負する日本は、いまや何処の病院でも成人病患者で溢れ返っている。そして、現代医学では、完治が難しい疾患も急増している。 医療現場では、様々な病気が種類別に分けられ、病気のランク付けなどの検査方法は発達しているように思えるが、実のところ、その治療技術は、細分化され、専門化されている。そして民間在野にいい治療法があっても、現代医学の治療法以外の、民間療法などは、一切認めないと言うのが今日の医療のあり方である。 さて、生活習慣病の元凶は、筆者が繰り替えし述べているように、細胞を錆(さ)び付かせる「活性酸素」が元凶となっている。 しかし、これを抑制し、除去できる「抗酸化物質」を人間は生まれながらに持っているのだ。 ところが残念な事は、近年、食生活の欧米化で「雑食」をする人が多くなり、それに加え生活環境が悪化して、体内に大量の活性酸素が発生する環境下での生活を余儀なくされている。その為に、体内で造る抗酸化物質の生産が追い付かなくなり、これが様々な難病・奇病を生み出しているのである。 活性酸素の元凶の一つは、「ストレス」なのだが、ストレスを容易に作り易い現代の競争社会と、情報化社会に生きる現代人は、こうした元凶から逃げる事は不可能になっている。 そして更に、こうした事に追い打ちをかけるように、環境ホルモン、酸性雨、ダイオキシンなどの化学物質の発生や、食生活の欧米模倣型の「雑食」は、現代人を更に不健康へと導き、白米、白砂糖、精白精製塩、乳製品、食肉、食品添加物などが、悪化に拍車を掛け、「抗酸化物質」の生産が間に合わないほどの、元凶へと駆り立てているのである。 つまり私たちは、世界的規模の様々な環境悪化によって、悪化の促進要因が複合的に重なり合い、「活性酸素の害」が蔓延(まんえん)した生活圏で生きている。この環境下では、ますます悪化に拍車が掛かるばかりで、健康的に生きる事が難しくなった時代だと言えよう。 その上、現代医学界は西洋医学至上主義が蔓延(はびこ)り、この呪縛(じゅばく)から未(いま)だに抜け切れずにいる。ガン患者への投与する薬品は、即効性重視の為、どうしても副作用の激しい抗ガン剤が遣(つか)われる。そして副作用の弊害により、更に患者を苦しめると言う、二重苦の悪循環状態に追い込まれ、末期患者の死に行く姿は、実に哀れなものである。 では、人間は何故病気になるのか。それは自分自身の躰(かだら)に存在する自然治癒力(ちゆりょく)が失われるからだ。 この為、ガンになっても治る人と、治らない人が出て来るのである。つまり、体力が無くて病気を克服できないのではなく、問題は「体質」であり、体質の優劣が、病気になっても治る人と治らない人を隔てている。したがって、体質を良くし、自然治癒力の働く状態に、自分の肉体を保っていなければならないのである。 健康維持の為には、普段からの自然治癒力が働き易いような、体質造りと、玄米穀物菜食の「正食」に心掛けることが大事であろう。 玄米穀物菜食といえば、よく「菜食主義」(【註】野菜と果物だけの食事で、玄米や玄麦などの穀類を摂らないのであるカリ塩を多く含む偏った食事)と誤解されるようだが、玄米穀物菜食と、菜食だけの食餌法(しょくじほう)は根本から異なるのである。菜食主義では、食品の中からタンパク質を補給する事が出来ず、極端化すれば栄養失調になってしまう。したがってベジタリアンと、玄米穀物菜食の「正食」をする人とは、基本的に異なっている。 この違いは、「夫婦アルカリ論」に詳細を述べているので、これを参照して頂きたい。 ここでベジタリアンと「正食」の違いの簡単に述べるのなら、前者は「雑食」である。つまり暗黙のうちに「カリ塩」を主体とした偏った食事内容であり、徹底的に肉類などの動蛋白を退ける主義である。 本来、「夫婦アルカリ論」は、カリ塩とナトロン塩のバランスの採れた状態を言うのであって、夫婦アルカリの差数量に、一定のバランスを見るというのが「正食」であり、則(すなわ)ち、そこには野菜ばかりでなく、玄米を中心とした「穀物」が加わるという事である。穀物を含めない菜食だけの食事は栄養失調になる恐れがあり、拒食症を度々引き起こす人は、穀物菜食の「正食」と、野菜オンリーの菜食主義を誤解して、拒食症に陥るのである。 したがって、「拒食状態」と「断食」も、根本的には異なるのである。断食をすると、拒食症になるから危険であるという医学者がいるが、これは断食が危険という事ではなく、断食に入る入り方や、遣(や)り方が間違っていて危険であるので、断食そのものとは、全く関係のない見当違いの意見である。したがって、家庭などで断食をやる場合は、しっかりとした断食指導者の指導を受けて行うのがよく、自分勝手な自己流の断食は、断食後にリバウンド(食への妄執などの餓鬼感)が起る為に非常に危険である。 ちなみに、家庭で行う、仕事をしながら、あるいは家事をしながらという断食は、最高「一週間」程度が限度であろう。これ以上の長い断食は、貧血や胃痛が激しくなり、十日間や二週間程度の断食を考えている人は、医療体制の万全な断食道場で断食するか、断食・絶食専門の内科医を訪ねるといいだろう。 さて、ガン発症のついて、話を戻す事にするが、現代の医学や科学からすれば、ガンは老化によって起る病気で、避けることができないものらしい。したがってガンと付き合い、共棲(きょうせい)する考え方も必要であろう。まず、ガンが発見されるルートを述べよう。 一つ目のルートは、一般の健康診断や人間ドックにより発見する方法である。早期発見、早期治療と云われるが、この状態で見つかるのは、ごく軽症に止まっている場合である。この段階では、だいたい1cm(1g)くらいといわれ、ガン細胞の数にすると10億個くらいで、それ以前の段階(ゼロ期)では小さ過ぎて、レントゲン撮影やCTスキャンには映らないとされている。そして自覚症状は殆ど無い。 二つ目のルートは、何らかの自覚症状が顕れた場合である。自覚症状はガンの部位や進行度によって異なるが、長期に亘って症状が継続する場合は、医療機関での治療が必要であろう。 現在のガン治療の主体は、外科的療法(【註】摘出手術。臓器などの一部を取り除く為、周辺の臓器との連携バランスが崩され、治療後には正常な機能が失われる危険性がある)であり、次に化学療法(【註】抗ガン剤投与。ガン細胞の発育増進を押さえる療法で、抗生物質、植物アルカロイド、ホルモン剤を投与。抗ガン剤の多くは骨髓に影響を与え、病原菌と闘う白血球などの細胞を造る働きを低下させ、病気に感染し易くなる。副作用と弊害があり、正常細胞も死滅させ、身体機能に大きな負担を掛ける)や放射線療法(【註】X線、γ線などの放射線を直接ガン細胞に照射し、皮膚ガン、咽頭ガン、舌ガン、偏桃ガンなどに用いる。細胞死滅後、その残骸が体内に残り、死滅せずに生き残る細胞もある為、依然として白血球の減少、それに伴う吐き気、貧血などの副作用を齎す。その上に、放射線照射により新たなガンを誘引する危険もある)などである。 さて、1996年、文藝春秋から一冊のショッキングな本が出版された。『患者よ、がんと闘うな』と言う本であり、著者は慶応大学医学部放射線科の近藤誠医師であった。この内容を吟味すると、手術は殆ど役には立たない。抗ガン剤治療に意味のあるガン発症は全体の一割。ガン検診は百害あって一利なし、という衝撃的な結論で締めくくられている本だ。 そして、これを更に吟味すると、次のようになる。
また、近藤医師のこの本は、「告発書」としての一面も持っている。 |