|
||
| ●ねじ曲げられた人間進化論 人間は、自我(じが)を内部に受け入れようと、更に進化し続けます。ここには自分自身の意識や行動の主体を指す概念が派生します。 それは主観と客観を区別することでも解るように、この区別が完了すると、ハッキリとした自我(self)意識が生まれます。 自我とは、哲学的に言って、認識・感情・意志・行為の主体を外界や他人と区別していう語であり、自我は、時間の経過や種々の変化を通じての自己同一性を意識しています。これは意識や行動の主体を指す概念であり、一般には「心」という言葉で顕(あら)わします。 この点は、人間が、猿や類人猿を先祖と同じくする高等動物の肉体を有しているのではなく、彼等とは種を異にする、霊界からの存在者であって、これが人間成立の過程に於いて、重要な意味を含んでいます。 また、人間の所有する自我は、良心の統制に従わせるような働きをし、これが人間以外の他の動物と大きな異なりを見せます。それは人間自身に、パーソナリティーまたは人格の側面が窺(うかが)われるからです。 人間の心の奥底には、イド(id)なるものがあり、これが本能的エネルギーの源泉となります。人間は快を求め、不快を避ける快楽原則に支配され、その後に、「超自我」が現れます。 超自我とは、イドならびに自我と共に、心を構成する三要素であり、自我から分化発達し、社会的価値を取り入れ、あるべき行動基準によって、自我を監視し、欲動に対して検閲的態度を保とうとします。 こうした「超自我」なるものは、人間を除いて、他の動物には持ち合わせません。それは人間が、他の類人猿と異なり、猿から進化した過程を辿らずに、人間特有の経路によって、人間が構築されたと言う事を顕わしています。 猿や類人猿が進化したとするダーウィン進化論は、十九世紀、ある作為と虚構理論によって、架空に想像されたものであり、これはマルクスやニーチェに劣らない虚構教説であり、こうした教説が、『進化論』として、未(いま)だ公然として、義務教育過程の中で幅を利(き)かせている事は何とも残念なものです。 そして、常識ある最高学府の出身者までが、ダーウィン進化論をすっかり信じてしまって、人間は猿から進化したと思い込んでいます。 しかし、こうしたダーウィン進化論に対して、欧米では多くの学者達が異論を唱えています。 生物学者として著名なR・エイブリー博士は、ダーウィン進化論に対して、 「自然界では同じ種は変化するが、絶対に進化など有り得ない。その証拠に、小麦は偶然が度重なってもグレープ・フルーツにはなりえないし、豚は空を飛びたい夢想を抱いたとしても、羽は生えないのである」と断言し、 また物理学者のF・ホイル博士は、 「ダーウィン進化論は、竜巻がゴミを巻上げたらジェット機が出来たというものだ」と述べています。 こうして考えますと、進化の過程で、総ての遺伝子情報の組み合わせを見ると、それら偶然に組み替えられる可能性は殆ど無く、それはゼロに等しいと言えます。 また、人間の先祖とされる、クロマニョン人(Cro-Magnon/旧石器時代末葉の化石人類。1868年フランスの南西部ドルドーニュ県で発見)の出現は、自然淘汰や自然選択による適者生存から、進化による生存の可能性はゼロに近く、ある種の外的な介入があったことは、人類考古学上の主流的な考えに落ち着いています。 ヨーロッパの化石人類中、クロマニョンは頭蓋(ずがい)の中等長のものの代表であり、ヨーロッパから北アフリカに分布し、現代の人類と同一種で、さらに長身だったという事を考えれば、洞穴壁に動物の彩色画を残すクロマニョン人が、果たして猿からヒトへと進化したホモ・サピエンス(Homo sapiens/知性人・叡知人の意で、現生人類の学名) だったのでしょうか。 また、猿や類人猿が、新人旧石器時代後期の人類にまで、物質的肉体的進化を遂げることが可能だったのでしょうか。 進化論では、ヒトの先祖がチンパンジーと分かれて類人猿になったと言う仮説が、現在では有力ですが、では、ヒトとチンパンジーとに分けれていって、最終的に人間になれなかった類人猿は一体系統樹の中の、何処にいってしまったのでしょうか。 常識的に考えても、人類は、猿から進化したとするダーウィンの説は、完全なでっち上げであり、彼の掲げた系統樹を始めとする十九世紀から今日までの仮説は、全くの虚構理論であったという事が解ります。 とすれば、類人猿と人類の先祖であるクロマニョン人とを結び付ける「ミッシング・リンク」(missing link/「失われた環」の意味で、生物の系統進化において、現生生物と既知の化石生物との間を繋ぐべき未発見の化石生物で、これが発見されると、進化の系列が繋がるという仮説)等、最初から存在しない事になります。 もともと、ダーウィン進化論の真の目的は、生物学上の進化論を首唱(しゅしょう)するより、生物学的仮説をでっち上げ、これを社会科学に反映させて、マルクスの唱えた共産主義虚構理論を、一般思想界に導入して、知識階級を一時的に頭脳マヒさせ、取り込む為の画期的な影響手段として、進化論がでっち上げたれた可能性が高いと考えられます。 したがって、人間を構成する肉体を含めた《霊》と《魂》の先祖は、猿や類人猿と先祖を共有する高等動物の肉体ではなく、更にもっと高度な霊界からの存在者であって、その存在は本来、霊的使命を帯びていました。 しかし、この霊的使命は、人間が霊体対肉体の配分比が1:9の、極めて霊体を軽視した肉体信奉主義に偏(かたよ)った為、霊体の心より、肉体の心の方に比重がかかり、霊的感覚を殆ど忘れてしまうという現象が起きたのです。 これは現代人の昨今の人倫の乱れ等からも克明に窺(うかが)われます。物質界に汚染されて「モノ」中心の欲望で動いている事は、霊体軽視の如実な現われであり、その霊体使命が「愛」であったことすら忘れてしまっているのです。 |
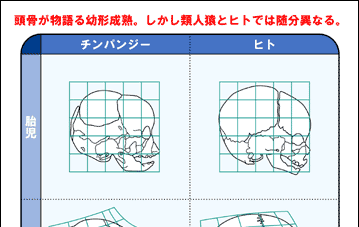 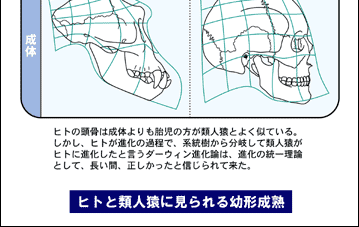 |
| ▲ヒトの成体の頭骨は、チンパンジーの成体よりも、幼児の方の頭骨に似ている。その為、今日の進化論では、ヒトは猿のネオテニーであるという考え方が有力である。ネオテニーとは動物が幼形のままで成長しこれを幼形成熟と言っている。ウイルス進化仮説では、ウイルスが猿に感染して、成熟に関する遺伝子を変化させる事で、幼形成熟による進化が起きたと説明する。ところが分子生物学が出現すると、ダーウィン進化論では説明できないような真事実が次から次へと現れ始めた。 |
| 本来の霊体使命は、自由なる人格と霊格に支えられた愛を実践する為の、第一段階の「熱」、第二段階の「気」、第三段階の「光」、第四段階の「生命」、第五段階の「感覚」、第六段階の「感情」を、次々に実現していき、ついには自我に相応しい体躯(たいく)を手に入れるというのが究極の目的でした。 ところがこの目的は達せられず、命体が地上に受肉すると、可視的現象のみに肉の目を向け、自己の欲望を拡散・膨張させて、肉体重視の信奉者に成り下がったのです。 というのも、ダーウィン進化論は、知識階級を虚構理論の中に取り込む、十分な説得材料を用意していたからです。巧妙と言う他ありません。 1960〜70年代にかけて、一部のインテリ層や学生らが、進歩的文化人の体裁のよいマルキシズムの煽動(せんどう)によって、マルクス・レーニン主義の虚構に情熱を傾けたように、ダーウィン進化論は、始めから意図的に用意されたように突然変異、自然淘汰、適者生存という基本的な枠組がなされていて、この枠組の中で、単細胞生物が、突然変異によって多細胞動物になり、やがて海中の魚は陸性化して陸に上がり、爬虫類へと進化し、その中のある種のものは翼を得て、鳥になったと説明しています。 そして今でも、こうした進化の過程を心の底から信じ、その理論に全く疑いを抱いていないという人達は、決して少なくありません。 しかし、こうした進化の過程を研究すると、やはり海中の魚が肺呼吸をして陸性化し、陸性化したものが翼を得るという進化の過程を追って一つの疑問に行き当たります。それは繰り返し偶然が起こると言うことからして、やはりそれは、確率的に言っても非常に難しいのではないかという疑念が起こります。 さて、進化を考える場合、いつも問題になるのは「種」という概念です。しかし、その「種」が、進化の過程に対し、どのような役割を果たしているか、現在でも全く解明されていません。それどころか、「種」と言うものが本当に存在するのか、という事すら疑わしくなってしまいます。 「進化」という語に導き出されるように、科学としての進化論は紛(まぎ)れもなく、ダーウィン進化論にはじまり、その著書『種の起源』は、これまでの「種の定義」を覆えし、当時としては一大センセーションを巻き起こしたのですが、『種の起源』は必ずしもその題名通りになっていないと言われます。 ダーウィン進化論では、生物が変化して生じた変種の突然変異が自然淘汰として働き、こうした後に変種から、また、更に新しい種が出来るとしていますが、一体どのくらい変化し、変種が発生しなければならないか、もっとも関心ある事柄については、ダーウィン自身が何も語っていないのです。 更に不思議なことは、ダーウィン進化論では、突然変異が起こったからといって、直ぐに進化する分けではなく、突然変異が繰り返し起こり、それが遺伝子情報として蓄積され、この状態に至ってはじめて進化するという点にあります。 こうした不思議な現象が、都合よく、何回も繰り返し起こるのでしょうか。 常識ある皆さんが、少し考えただけでも解るはずだと思いますが、喩えば、爬虫類から鳥類へと進化する過程の中で、ダーウィン進化論を適用すると、爬虫類の前肢が羽に進化するという突然変異を辿るわけですが、こうした多くの変化が、整然と突然変異を繰り返す為には、一体どれくらいの突然変異が必要になるのでしょうか。 更に大事なことは、前肢(ぜんし)が羽に突然変異すると言うだけではなく、その羽を動かす為の脳も同時に進化しなければならない必要性に迫られます。地上で這(は)い回っていた爬虫類が突然変異によって羽を持ち、それを動かして空中に舞い上がるのですから、仮に羽が生えたとしても、骨を中空にして、全体重を支え、その為には体重を減少させるという働きと同時に、空気抵抗を少なくする為には急速な体の変化が求められます。 こうして考えてくると、突然変異によって爬虫類が「空を飛ぶ」という事は、気の遠くなるような時間と、無限回数の突然変異が繰り返し起こり、然も「同時代に、同時に都合よく起こる」という条件が揃わなければなりません。 |
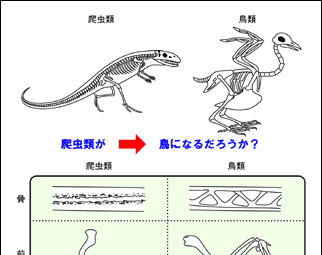  |
| ところが、ダーウィン進化論では、突然変異は「偶然」にしか起こらないのです。このような変化が、一つの個体に対して、何回(実際には途方もない回数)も偶然が重なって起こるものでしょうか。 それも、もし突然変異が起こるとして、同時代に生きた生物たちは、ほぼ同じ速度で変化が起こらなければなりません。現実にこうした繰り返しが、果たして都合よく地球上で起こっていたのでしょうか。 また、適者生存の生存競争にも大きな矛盾が生じます。 ダーウィン進化論では、適者生存という形をとるのであれば、総ての生物はお互に生き残る為に闘争を繰り返さなければなりません。この激しい生存競争に生き残ったものだけが適者として、子孫を作る事が許されます。 ダーウィンはこの闘争を「struggle for existence」と呼んでいます。日本語訳では「生存競争」あるいは「生存闘争」と訳されています。 さて、生物とは、生存競争に勝ち抜く為に、生物同士が激しい生存競争を繰り返すのでしょうか。 生物の生息する意味は、戦いや闘争を繰り返すだけの存在ではなかったはずです。ところがダーウィン進化論では、生物が自らの子孫を増やす為に生存競争は必要不可欠な条件であり、これがダーウィンの進化論には欠かせない必須条件になっているのです。 こうしてダーウィン進化論を突き詰めると、まず人間中心的な説明に素朴な質問が集中し、更に系統樹を取り上げて見ても、猿が類人猿になり、類人猿が人間になったとするならば、途中で類人猿になれなかった猿、あるいは人間になれなかった類人猿は一体どうなったのでしょうか。 この事は、系統樹の何処にも出てきません。 進化論の課題には、適応・系統・分岐という三つのテーマがあります。このうち、ダーウィンは「適応」に最も力を入れました。ダーウィン進化論や総合進化仮説は、生物が環境に適応して生き残る事から進化が始まるとしています。しかし、こうした観察と実験を繰り返してみても、進化に繋がる直接的な適応は殆ど見つかりませんでした。 ダーウィン進化論が完璧(かんぺき)な理論家と言うと、どうもそうとは言い切れません。分子生物学によって諸々の真事実が発見されると、ダーウィン進化論は揺らぎ始めました。 これは日本人の多くが、十七世紀のニュートン物理学を「科学」として捕らえ、物理現象の総てがこの科学によって解明されていると盲信しているように、またダーウィン進化論も、生物の進化の過程を完璧に説明出来るものではなくなってきています。 |