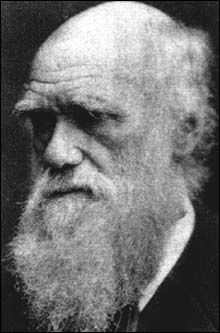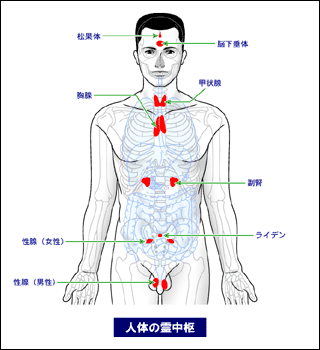|
||
| ●霊主体従の思想から生まれた霊的食養道 霊主体従に思想から言えば、身体の世界は生命体(生体と命体の合体で、肉体と霊体を顕わす)としての存在として置き換えられる事が出来、その生命体の形の中で、霊的な作用を読み取り、体的体験として、それを実践していくのが《霊的食養道》です。 人間の行動には四つのものがあり、それが心の機能として活動源となります。可視的には思考と感覚があり、不可視的には直感と感情があります。 |
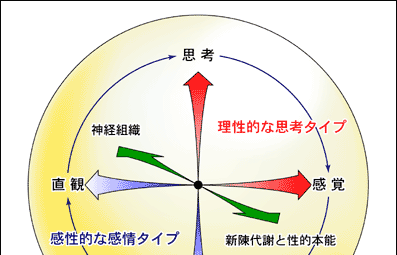 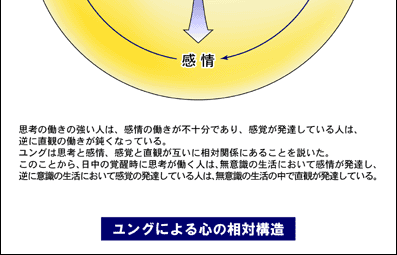 |
|
心の相対構造は、まず可視的なものと不可視的なものが相対し、次に思考と感情、感覚と直感が各々を縦軸と横軸において相対します。そして各々に因果関係を持ちます。 喩(たと)えば、新陳代謝エネルギーと思考エネルギーは共通性があり、したがってセックスも、抽象的な学問も、同一エネルギーを必要とするように、日常遣っていないエネルギーを駆使しはじめると、急激な集中力が必要になり、そこに遣われるエネルギーは、今まで他に流れていたエネルギーが、これに当たる分けですから、身体の健康については今まで以上に意識的に注意しなければならないという必要に迫られます。 それと同様に、今までの日常生活の中で、自分の良い能力と悪い能力が混乱していた為に、その人自身の優れた部分も、悪い部分で相殺されて、市民的な安定のもとに生活を営んでいたわけですが、つまりこれは個人的な営みではなかったという事にもなります。 ところが、支配体制の人民を微生物視して見下す眼下から一歩外れると、ある時点から、突然、内面生活に変化が生じ、それは丁度、泥で汚れていたコップの中に沈殿現象が起こるように、重い泥は底に沈み、軽い部分は上部に浮上して、やがてそこには透明な部分が見え始めます。しかしこうした現象が現われると、ネガティブ(negative/否定的または消極的)な部分も浮上して、今まで隠れていた部分が顕在化します。
つまり、魂をコントロールするべきはずの自我が制御不能になり、パニック状態に陥るのです。これが一般に言われる、「自我の潰(つぶ)れた状態」を指す、精神分裂病です。嫉妬や憎悪が剥(む)き出しになるのもこの病気の特徴です。 この意味からすると、非常に能力を持った人でも、大きな危険を内在させている事になります。喩えば、話していると非常に立派なのですが、やる事が何処か狂っているという能力の持ち主がこれに当たります。 こうした人は政治家に多く、普通想像できない事を平気でやる人達です。政治家の汚職は欲望と想像が膨張したときに起こりますし、もっと輪を掛けて悪辣(あくらつ)なのは、ナチス・ドイツ時代のヒトラー傘下のヒムラー(ナチス・ドイツの親衛隊司令官)やゲッペルス(ナチス・ドイツの宣伝相)と言った、こう言う人も、知的能力が優れているのですが、全体を総合して見ると、自我の働きがうまくコントロールされていない事に気付きます。 広い意味での、霊的波調のリズムに混乱を来しているといえるでしょう。これが「魂の波調周期の乱れ」というものです。 では、こうした「魂の波調周期の乱れ」は何処から起こってくるものなのでしょうか。 一つは、食の乱れにあると考えられます。 したがって食の乱れを修復すれば、やがてこうした乱れは消滅に向かい、食に慎みを得る意識が芽生えます。この意識の芽生えを食養に応用したのが《霊的食養道》なのです。 内在的な魂の作用として、動物性食品や乳製品た鶏卵などを多く摂取すれば、当然そこには血の濁りが生じます。そしてこの濁りは、沈殿作用を起こした場合、上に軽い物が浮き上がり、下に重い物が沈みます。そして全体的にはどんよりと濁っているのですが、それでも上部には幾らか透明に近い箇所が現われます。 この突如現われた透明から、嫉妬や憎悪が剥き出しになるのです。精神分裂病の禍根は、実にここに内在されていたわけです。 しかし、玄米穀物を主食に、海藻類や植物性食品を副食にしている人は、普段から血の濁りという現象が起こっていないのですから、そこに見えるものは常に濁りの少ない透明感があり、透明を通して、物事を見ていますから、嫉妬や憎悪の意識は非常に低く、「見通し」の利(き)いた思考と行動で、未来予測が判断できるわけです。 ●人間の源初の熱体・気体・光体の定義 人生修行の究極の目指すところは、健康体を維持しつつ、更に丈夫な体躯(たいく)を養い、究極的には霊主体従を目指して、半身半霊体(はんしんはんりょうたい)の体躯を自分自身に課して、それを造り上げる事にあります。 飢えを始めとして、暑さ寒さにも平然として耐えられ、然(しか)も、堅固な精神力得る事であり、また一方、食の世界においては、霊主体従の理想の可能態を体現していこうとするのが、究極の目的です。 その目的に最終課題は、人類の最終進化に対し、それを受け入れる準備を整えることです。 地球がこれまで以上に汚染が激しくなり、当然、放射能汚染もこれに加わり、未曾有の阿鼻叫喚(あびきょうかん)の現実が出現することは、もはや隠しようのない事実となってきています。それにこれからの食糧危機は深刻であり、それに加味して、土壌を汚染や緑地の砂漠化が叫ばれています。科学の発達と共に、遺伝子組み替えが当り前のように取り沙汰され、組み替え食品が地球を覆い、この地上は悉々(ことごと)く破壊されることが予想されます。 こうした状況下、大自然は人間に対し、最終進化を迫ることは必然的な流れであり、古代史を紐解くと、こうした大異変・大激変と共に、人類への進化を促してきました。 さて、ここで「進化」を定義としているのは、ダーウィン的な適者生存や自然淘汰の進化論ではなく、また生存競争に勝ち残るというものでもありません。 霊的食養道の教える「人類の最終進化」とは、生体並びに命体を維持する為に、どうしても進化の過程をとらざるを得ない霊的進化を言います。 シュタイナー(Rudolf Steiner/オーストリアの生れのドイツの思想家であり、菜食主義に徹したピタゴラス派の人智学の創始者で、菜食主義者の黒魔術の実践者ヒトラーの宿敵とされた。1861〜1925)は、独自の人智学を提唱し、芸術や教育など多分野で活動した、オルターナティヴ運動の先駆として有名です。 彼の特異な基本的な観想法の一つに「薔薇十字(ばらじゅうじ)」なるものがあります。 これは神智学を人体に置き換えて発展させたもので、人間の存在を植物に対比させるものでした。またこうした瞑想法が薔薇十字団の霊的思想に繋がっていき、神秘主義秘密結社・フリーメーソンや、上部組織のイルミナティ(フリーメーソンを傘下に収める秘密組織で、1776年、南ドイツ・バヴァリアのインゴルシュタット大学の法学部教授であったアダム・ヴァイスハウプトによって設立された秘密結社)へと受け継がれます。 以降、経済や政治の中に神秘主義が持ち込まれ、自由と平等を標榜する近代の革命的啓蒙思想により、大衆が煽動されるという事態が起こります。その結果、アメリカ独立戦争が起こり、フランス革命が起こり、カトリック教会の急進派への攻撃が起こり、ロシア革命が起こり、民衆はこの中にある種の意図をもって誘導されていく事になります。 さて、人間は進化論が教えているように、物質的存在から動物的存在に移行し、その通過過程において肉体を有し、現在の肉体になったと考えられています。 この考え方は、十九世紀以降のダーウィン以降のものではなく、古代から考えられていた観念であり、進化していく過程の中には、物質界での因果関係では説明できない作用が、進化を目的として働いたことを意味します。そして、そのつど霊界から、何らかの作用が働き、本当の進化は物質界以外の全然別な作用として具現されてきました。
したがって人間の所有する肉体は、物質の進化が特定の段階まで到達し、それは飽和状態を越えると、臨界点を通り越し、霊的な実体がそこに現われてきて、受肉されるだけの肉体的条件が整い、それがヒトの誕生であると考える思想です。 したがって、人間の本性は、物質界の肉体だけではなく、肉体を結び付いた霊体が、そもそもの実体であり、その結果、肉体を通じて現在地上に生息しているが、その存在が本当に成立しているのは物質界ではなく、霊界だというのです。 こうした考え方は、ダーウィン進化論以前の、日本の古神道にも共通した思想として、東洋思想の優を誇っていたのですが、十九世紀、これが一旦否定され、再び東洋哲学の研究者として有名なユングらによって浮上し、更(あらた)めて「人間とは何か」という、ダーウィン的な発想とは異なる人間観が出てきたわけです。 人間が肉体を主有する以前の初期の人間にとって、肉体が存在しないばかりでなく、感情も、意志も、もちろん表象能力や、感応能力も存在しなかったという、最も源初的な初期の状態が考えられます。 こうした状態下に、霊的な存在界が出現し、最初に起こった現象は「熱の流出」だと言われます。 本来の熱学上の概念からすれば、熱とは常に分子運動の在(あ)り方次第で、変化する物質の属性と考えていますから、個体も液体も気体も存在しないところに、突然、熱だけという考え方は受け入れらるはずはないのですが、しかし、霊的に考えた場合、熱はあらゆる物質の存在形式の中で、最も霊的な現象と存在をみます。 本来、熱力学では、熱平衡にある系で、「準静的に加えられた熱量を、その系の絶対温度で割った値をエントロピーの増加分と定義する」となっています。 また可逆変化なら、エントロピーは一定で、不可逆変化では、必ず増大するという熱力学の第二法則がこれを裏付けます。 しかし、霊的存在に近い熱の概念は、物質界においてもその存在形式が「熱の流出」と考えます。 これは喩(たと)えば、熱の測定を行う寒暖計一つ取って見ても、同じ空間を個別に間仕切り、細かく空間域を遮断したにもかかわらず、そこを寒暖計で測定した場合、部屋全体は20℃を示しているのに、暖かく感じる場所があったり、あるいは寒く感じる場所があるように、人間の場合も暖かい人と、冷たい人が存在するように、個人の主観で暖かい部分と冷たい部分が発生します。 また、想像力一つで、心の中の作用として寒暖の差が生じ、物質界からはなれた世界でも、こうした寒暖の差が生じている事が解ります。したがって、熱とは、物質界だけに存在するのではなく、熱が独立した存在であり、既に霊魂の世界にも関与して発生しているのです。 そうした結論から、私たちの躰(からだ)の内部には、体温とは異なる「熱」が発生している事が解ります。 体温は物質界の肉体現象ですが、病気は躰以外の熱の寒暖の差から発生します。健全な場所は暖かく、病める場所は冷たい箇所が存在します。 憑衣・憑霊が背後から忍び寄り、頸の付近の「風門(ふうもん)」から侵入して来て、毛穴である「気門(きもん)」を遮断してこの出入口を塞ぎ、頸椎(けいつい)の上って亜門宮(あもんきゅう)に居座り、人体の体温調節機能を破壊するのは、こうした「熱」の遮断にあると考えられます。また、憑衣・憑霊直後は、ゾクゾクとする悪寒を覚えるのは、霊的な感覚からであり、決して肉体が感じた寒さではありません。 また、何かに夢中になって考えたり研究に打ち込みますと、そこには熱が集中し、あるいは別の亢奮(こうふん/感情のたかぶること)状態においても、躰は熱が循環するエネルギーの通路となっています。 この循環は血液の循環と並行するもので、決して血液そのものではありませんが、もしこの熱を物質的な最初の根源と考えますと、この存在形式は、「熱体」をもって、人体様式の源初的な存在形式であったと考える事が出来ます。 こうした熱体を発想上の出発点に置くと、それに続く何億年という進化の過程の中で、当然、それを運行する「気」という存在が発生します。気は、動物の場合は酸素の吸入であり、植物の場合は炭酸ガスの吸入として、呼吸器管を司る象徴としての現われが起こります。やがてこれが躰の活動として参入し、不要になったものを呼気として体外へ輩出します。 つまり、人体様式は熱の作用と気の運行により、頭の天辺から脊柱を通して足の爪先、あるいは手の指先までに循環させ、これが人間の独特の呼吸法となっているわけです。胸式呼吸であれ、腹式呼吸であれ、呼吸の原点はここにあります。これが「気体」です。 そして熱だけの存在時には、まだ「光」というものはありませんでしたが、これに呼吸が伴い、気が発生すると、外界との関係を積極的に持ち始めた時点で、生命活動がはじまりました。 この生命活動がはじまった時点が、光を発した時点であり、人体は光という特異な輪郭を持つに至るのでありますが、源初にはハッキリとした輪郭を持たず、固定しない初期には単に膨張と収縮を繰り返すだけでした。 ところが、これがやがて時間を経て、定着し、多彩な微光を発する「光体」と変貌していきます。 こうした人間への第一歩が、熱体であり、気体であり、光体であるというプロセスを辿りながら、人体の幻想的な形姿が更に進化し続けるのですが、今度は呼吸だけではなく、外界に対して、共感と反感を伴うようになり、源初的な主観という感情を持ちえる結果にまで進化を遂げます。 こうしたプロセスを経由して、人間の本性は大きく分けて鉱物、植物、動物の形態を形造りながら、進化の過程を辿ったと考えられます。 それでもこの段階では、まだ人間は物質的観点からすると、差程、輪郭が定かでない流動体的な存在でしにしか過ぎませんでした。 この時期、地球においても、今日のように大気と大地は明確に区別されておらず、大地は溶岩状で、沸き立つ流動の液体でした。また大気においても、非常に濃密な、靄(もや)のような暗雲が立ち罩(こ)めていました。 この天地の濃厚の大気中を、人間の本性は浮遊しながら、人間存在として、源初の呼吸作用から、感情のままに、何か好ましいものに接近しようと企てていたのです。 さて、人間の本性は遠隔通信、遠隔治療、幽体離脱、瞬間移動という異次元空間で起こる脱魂現象(哲学的には、魂の脱離の意味で、人間が神と合一した忘我の神秘的状態をさす。フィロン、新プラトン学派、中世神秘主義思想家の重要な概念)をこなせるのですから、この実体は「霊」という事になります。 霊は元来、超時空の存在界の所産で、その本質は意識でありますから、もともとは肉体を持たないというところにあります。肉体を持たないのですから、それ自身では物理的な作用を発生させることが出来ません。そこで、何らかの物質界の肉体が必要になり、これにうまく潜り込んだのが、水冷式哺乳動物で、霊長類の最高峰である類人猿でした。そして彼等の肉体をコントロールし始めたのが、人間という動物形式の乗り物でした。
人間は、今日の形態にまで発展していく過程の中で、松果腺(松果体/左右大脳半球の間、第三脳室の後部で、視床枕と中脳の上丘との間の陥凹部にある小さな松毬状(まつかさじょう)の内分泌器官。メラトニンおよびセロトニンを分泌。メラトニンは生殖腺に抑制的に作用し、その産生は光に影響される。鳥では生物時計として働くとされている)、つまり額の眉間と眉間の中間点に、内在的な共感と反感があり、今日の退化以前には外形と結び付いた器官と考えられます。そしてその器官は、霊的作用を受けて、最初の人間の感覚器官となって働き始めたのです。 |