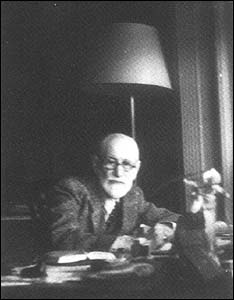|
||
| ●愛の想念は高次元世界から発せられる 「愛」の概念を繰り返しますと、その意識体は自他において「同一」であるということです。自他の区別がなく、自他に境界線を引かない事が「愛の現れ」であり、それは再び「愛する想念」に回帰します。 また、この反対想念が「愛のない想念」であり、《愛とは何か》と言うと、「自他共に同格」であり、「自他共に同等」であり、「自他共に同価値」であり、これこそが同一体の重要な要となります。 そして、同一体である事の認識から生ずる「思考」および「言動」は、同一体認識の上で、格差を設けないと言う事です。 これを「愛のない想念」から表現すると、自他とは、共に異質のものであり、その間には差別や意識の上で優越感があり、その優越感が自他離別を働きかけ、ここに「愛する想念」とは反対想念が、人生に反映されて、「愛のない想念」に脱落して行く現実があります。この現実こそが、不幸現象の実態であり、こうした想念が、世の中全体を悪想念へと導いて行きます。 具体的に言えば、「恨む」「憎む」「妬む」「羨む」「侮る」「悔しい」「惨じめ」「哀れ」「情けない」等の悪想念です。 そして悪想念を抱く心には、次のものがあります。 |
|
悪想念心
|
意識と行為
|
跳ね返り現象
|
|
傲慢心
|
驕(おご)り高ぶって人を侮る。横柄。威張る。夜郎自大。見下して礼を欠く。敗者を甘く見る。やり込めて満足感を楽しむ。無礼な態度をする。 | 味方や部下から裏切られ、やがては寝首を掻かれる。 |
|
優越心
|
他より優れ勝ることを自慢する。貧困者を見ていい気味だと思う。ホームレスを見て臭い、汚いと思う。落ちた者を更に叩く。貧乏人を下賎と看做し卑下する。 | 年齢に関係なく、いつまでも煩悩がチリチリと焦げる。 |
|
妥協心
|
折り合いを付けて流れる。何事も運命と諦める。お追従をする。誇りを持たない。安易な考えに流され易い。丸め込まれ、妄信し易い。 | 神経質になり、狡猾な人間からカモにされ易い。 |
|
競争心
|
勝負や優劣を互いに競い合う。あいつと自分が同格であってたまるかと思う。負けまいとする意識。 | 約束を取り付けても履行されず、土壇場で覆される。 |
|
恐怖心
|
恐ろしく感ずる。暴力を恐れ、不正にも屈する。怖れや不安を抱く。先の事を思い悩む。恐れに驚く。 | 精神的破壊。 |
|
溺愛心
|
理非を分別なしに可愛がる。子供への過保護愛。特定な者だけを美しいと思う。 | 凡庸さが命取りになる。 |
|
利己心
|
自分一人だけの利益を計る。我が儘。自分中心。極度なボランティア意識で、利他的を装おう。 | ハレンチなことをして恥を掻く。 |
|
後悔心
|
以前した事を後になって悔いる。人からやり込められたと悔しがる。惜しいと思う。憤懣やる方ない気持ち。過去を懐かしがる。 | 重い労働感と、徒労に終わった疲れが充満する。 |
|
逆上心
|
激しい怒りや悲しみ等の為に取り乱す。自分の非を指摘されて反論して居直る。弁明や言い訳をして非を回避する。自分を棚上げにする。 | 陶酔に誘い込まれて、盲目となる。 |
|
誹謗中傷心
|
他人を非を吹聴する。人の評論をする。悪口や陰口を言う。無実の事を言って他人の名誉を傷つけること。 | 利害の違いで、陥れられる。 |
|
羨望心
|
妬みや羨ましいと思う。自他との境遇を比較して嫉妬を抱く。 | 足許に火が点く。 |
|
敵愾心
|
敵と争おうとする意気。傷つけてやりたい。殺してやりたい。憎い、相手に向かって感情から「死ね」と念を発する。 | 無意味な狂躁に襲われる。 |
|
失望心
|
あてが外れて、がっかりする。希望を失う。厭世観(えんせいかん)に陥る。自分が貧乏症ではないかと嘆く。 | 苦悩を背負わされ自滅する。 |
|
自虐心
|
自分で自分を責め苛(さいな)む。自身を傷つける。自分が苦しむ事によって罪の呵責から逃れる。 | 人生からの逃避行を繰り返す。 |
|
猜疑心
|
人を嫉(そね)み疑う。不信を持つ。人を信じない。 | 嫌疑を受けられて、迷いばかりが浮上する。 |
|
闘争心
|
鬪い争う。好戦的思考。弱肉強食主義。立場の逆転を窺う。転覆を企てる。 | 捕縄を打たれて護送される。 |
|
侮蔑心
|
人を軽くみてバカにする。侮ってない蔑ろにする。人を甘く見る。人を蔑む。一蹴する。一瞥する。 | 踏み付けられる。 |
|
自負心
|
自分の才能や仕事に自信や誇りを持つことであるが、「こだわり」が起こると、小さい事に執着して融通がきかなくなる。思い上がる。自惚れる。つけあがる。 | 堆積した不満が爆発する。 |
|
卑下心
|
自分を劣った者として卑しめる。へりくだる。金持ちを英雄視する。自分を下において謙遜する。 | 耳を傾けて聞いてくれる者がいなくなる。 |
| 以上は悪想念のほんの一例に過ぎませんが、これ以外にも悪想念があって、これが自他差別や自他離別から生じた想念であれば、それは総(すべ)て「愛のない想念」となります。 「愛のない想念」は無数に存在する為、私たちは日々反省を繰り返して、悪想念を消去していかなければなりません。そしてこうした悪想念は、一挙に消去してしまう事も可能です。それは全く簡単な事です。 要するに、積極的に「愛する想念」を抱けばよいのです。「愛する想念」のある処に「愛のない想念」は、入り込めないからです。 ここで、私たちは再び「愛する」という真の意味を認識しなければならないのです。そして「愛する」とは、自他共に同格《同等》《同格》《同価値》で、それは総てが一体だと観(かん)じる事なのです。 ●世間に吹き荒れている八風 世間には「八つの風」が吹いています。これを「八風(はっぷう)」と言います。 八風とは、喜怒哀楽や一喜一憂の中に潜む「風(ふう)」の事で、八つの、人間を翻弄(ほんろう)する風の事です。そして人は、この風の中で人生を経験していく事になります。 |
|
「利」
(り) |
損得勘定から起こる一喜一憂。また都合のよいこと。更には、賢いこと、狡いこと。よく切れる人に対して言う。 |
|
「衰」
(すい) |
地位の上下を喜んだり悲しんだり、あるいは悔しがる心の乱れ。また衰頽・衰弱・老衰・盛衰などをさし、衰えることを言う。 |
|
「毀」 (き) |
人に蔑まれたり、惨じめに感じたり、後ろめたさを感じたり、人を非難したり、誹ったりする心の底に潜む圧力。また誹(そし)ることや貶(けな)すことを言う。 |
|
「誉」 (よ) |
地位や名声を得ることで、褒(ほ)め讃えられる事で傲慢(ごうまん)なったり、豪語を発する慢心。「ほまれ」は自分の裡側(うちがわ)に存在している時は、何の害も与えないが、一旦外側に向かうと、称誉・名誉・誉望へと変貌(へんぼう)する。 |
|
「称」 (しょう) |
知らない間に、人々に賞賛され、突然の喜びに吃驚(ぶっくり)すること。何らかの「賞の対象」にノミネートされた時に起る。称賛・称揚などがこれにあたる。 |
|
「譏」 (き) |
人から悪口を言われたり、陰口を叩かれて、その後、人の善意や諌言を悪意と受け取ってしまうこと。悪しざまにいう、悪くいう、非難する、貶(けな)す。 |
|
「苦」
(く) |
落ち目になって、失望し、人生の終わりと受け取ったり、破滅と受け取って、もがき苦しむこと。 |
|
「楽」
(らく) |
万事物事が旨く言って、仮初(かりそめ)の順風満帆に気を良くし、局面的な幸せに有頂天になること。 |
| 人の世は、「苦」であると説いたのは、お釈迦さまです。 あらゆる事象には「苦」が入り込みます。この「苦」は、人間だけが所有するものではありません。こうしたものは動物にもあります。動物の多くは、生きながらに、自分の肉体を貪(むさぼ)りつかれる苦しみがあり、この苦しみを解消する方法を知りません。 小さな動物は、大きな動物の餌食(えじき)になり、逆に、小さな動物は大きな動物の死角を突いて、躰の窪(くぼ)みを食い荒らします。常に、弱肉強食の食物連鎖の中にあって、他の動物の隙(すき)を窺(うかが)い、隙あらば、他の動物を喰い物にします。そしてこの「輪」の中から、一歩も出られません。 また、「出よう」という智慧(ちえ)もありません。 他の動物から食い荒らされたり、人間から殺されて、食べられます。あるいは老いるまで使役されたり、役に立たなくなれば殺されます。いつもビクビクしながら、周囲を警戒したり、自由で伸び伸びと、寛(くつろ)ぐ時間等ありません。自由は全く奪われたままです。 喩(たと)えば、羊は飼われて毛を取られます。虎や熊やライオン、銀狐やビーバー等は、毛皮の為に殺されます。麝香鹿(じゃこうじか)は角(つの)目当てに、猟師から狙われます。 しかし彼等には、まだ少しだけ自由があります。もっと悲惨なのは、殺されて、自分の肉を喰われる牛や豚達です。彼等は殺され、肉を喰われる為に生まれ来て、飼育されます。 牛や豚達は、濃厚飼料で肥らされ、余念なく餌を食べ続けさせられます。なるべく動かないようにして、骨を細くし、肉の「歩留(ぶどま)り」を狙いとして飼育されます。肉をつける為に、徹底したゲージ飼育が行なわれ、食欲を増す為にビールまで飲まされます。出荷前には抗生物質が密かに投与され、糞尿の臭いを消す為に酵母菌まで口の中に押し込まれます。 そして、ここに「生命」の営みはなく、人間側のエゴイズムだけが存在しています。 こうした動物の彼等は、自由を奪われながら、そこから抜け出す術(すべ)を知りません。自分でどうしたら良いのか、それを考える事すら出来ず、「生」の本質を見ず、また果てしない苦しみの中にあって、そのまま埋没して行きます。 動物の心と魂は、「愚かさ」で曇らされています。小空間の共同体のゲージ飼の中で、殺される日を待ちながら、希望のない歳月を送っているのです。無知の中にあって、自分では、どうすることも出来ない苦しみを抱えています。そうした動物の無念も、この非実在界の中には蔓延(まんえん)しているのです。 そして人間もまた、彼等とは異なる苦悩を抱え、多くの人の共通的な想念は「わたし」が世間の八風に吹かれながら、年老いて死んで行くと言う事を「怕(こわ)い」と思うようになります。 これが、夢や幻影のような想念の世界に囚(とら)われていることから起こる「恐れ」であり、「悲しみ」です。 この意味から、人間もある種の輪廻の中に閉じ込められて、この輪から一歩も抜け出すことが出来ません。まさに、人間は動物を以上のように扱い、自らのエゴイズムを満足させる為に動物をゲージ飼するのですが、人間もまた、運命の輪から抜け出すことが出来ず、人の死を、動物が屠殺場に向かう時のように、尻込みをし、脚を突っ張り、貌(かお)を左右に振ってイヤイヤをし、「死ぬ」という現実を悲しく思うのです。 それは、人の一生と言うものが、喜怒哀楽や一喜一憂の中に集約されているからです。 ●霊主体従の思想 唯物論と唯神論(唯心論とも)が常に対峙(たいじ)し、反目した経緯は、歴史を見れば一目瞭然(いちもくりょうぜん)です。 そこで両者の対極に対し、理想論が登場しますと、またこれに対峙して、新たな現実論が現われてきます。 現実論とは、理想的な思考に対し、現実が直面する様々な問題点を上げ、理想はあくまで理想の範疇(はんちゅう)にあり、そこから逸脱するものでない事の説論を掲げました。 したがって現実論は、実際に起こっている物事を、現実では揺るがし難いという判断を下し、それを必然的な営みと定義づけます。 この営みは、現実社会そのものを直視し、その発想が理想論と、常に対極するという図式の上に引きずり出し、理想論は一種の可能態であるとは認めながらも、その一方で、概念と内容は到底克服し難い論理であると決めつけ、こうした思考がやがて、諦めにも似た、希望や期待の否定を打ち出していきます。 更にこうした発想下に、「宿命」という、人知では如何ともし難い現実があることを、私たちに突きつけます。 さて、こうした現実下にも、理想論は可能態の態度を取り続けます。 それは理想論が、単に概念に止まらず、それ自体で単独している存在観があるからです。こうした存在観に、目を付けたのが、ユング(Carl Gustav Jung/スイスの心理学者・精神医学者)でした。 ユングは最初、ブロイラー(Eugen Bleuler/スイスの精神医学者。精神分裂病という名称を提唱)に協力し、連想検査を作り、また、性格を外向型と内向型に分類した医学者です。 はじめ彼は、フロイト(Sigmund Freud/オーストリアの精神医学者)に共鳴し、フロイトの説く、人間の心理生活を、下意識または潜在意識の領域内に抑圧された性欲衝動(リビドー)の働きに帰し、深層心理解明の手段として、精神分析の立場を支持し、精神分析運動の指導者になりました。しかしその後、フロイトの学説を批判し、独自の分析心理学を創始しました。 その特異性を、理想家の考え方に適用しますと、その発想は総て「心が作り出したもの」という事になります。
何事も心の所産であり、もし心の存在が幻想であったならば、この現実の一切の事象もまた幻想になってしまう。そして存在する根拠を辿って行けば、必ず「心」に帰り着くはずだと言っているのです。 ユングのこうした考え方を「唯心論」と言います。 ユングは自身でも霊的体験を繰り返すうちに、晩年は近代科学者としての立場があやふやになってきて、物質の世界は、物質界で個別にこの世界が独立しているのではなく、これに大きく関与しているのは、一見、別世界に見える霊界があり、これが物質界と関係しつつ、何らかの営みをしているのではないか、と考えるようになります。 かつて出口王仁三郎(おにざぶろう/わにざぶろう)が、「霊主体従説(れいしゅたいじゅうせつ)」を唱えましたが、ユングの考え方はこれに非常によく似ています。 この霊主体従の思想によりますと、まず霊的なものが存在していて、それに追随する形で、身体の世界が生まれ、そこに現実の世界が出現したという事になります。 したがって私たちが、何か、実際に行動したり、限りない欲望を燃やすのは、それに関与する霊主体従によって、霊的世界の結果が現世に現われたとする考え方をします。 換言すれば、霊的世界の存在を知れば、そしてその世界で起こっている特異な事象を知れば、それはいつか、私たちの肉体においても、実現化されるのではないかという、予言的な可能態をとっていく事になります。 |
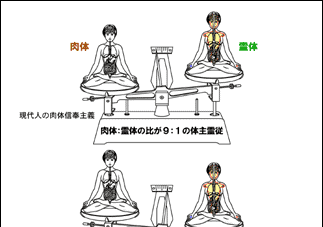 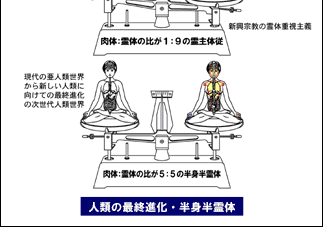 |
| ▲肉体:霊体の分離比が「9:1」の霊主体従か、それとも「1:9」の体主霊従か。いま、人類は半身半霊体としての最終進化を迫られている。 |
| 創造のプロセスから言うと、まず、霊界があり、そして現実世界に肉体の世界が現われた。この肉体の世界は、人間が、本来は霊主体従でありながら、肉体対霊体の配分比が逆転してしまった為に、もともとは「9:1」の霊主体が、肉体に偏り「1:9」の逆転関係になってしまって、肉体の感覚だけで、肉体を「主」とするようになってしまったと言うものです。 唯心論や唯物論が「唯」と言う文字を用いるのは、その霊体対肉体を配分する上で、大きな意味を持っています。 ちなみに「霊主体従」とは、人間の本体は霊体であり、それに従うものが物質界の肉体という意味です。したがって霊体が存在する霊界で起こっている事は、必ず肉体が棲(すむ)む現世の物質界でも、同じことが起こるという事を意味するものです。 ●ライプニッツのモナド論 近代科学が、唯物論の唯物弁証法や唯物史観から生まれた事は周知の通りです。 したがって可視現象だけを捉え、これを基盤として自然科学を発達させてきたわけですが、それは物質界にこだわった事象を捉えただけに過ぎませんでした。 ために、可視現象は捉える事が出来ても、不可視世界のものは何一つ測定したり、予測したり、捉えたりする事が出来ませんでした。今日の自然科学が万能でない事は、便利さや豊かさや快適さを追求した結果、現代人への恩恵とは裏腹に、この科学が既に暗礁(あんしょう)に乗り上げ、座礁して身動きが取れなくなっているのは周知の通りです。また一方で、様々な汚染物質を蒔(ま)き散らしている事は明白な事実となっています。 そこで現代人に迫られるこれからの課題は、人類が最終進化に向けて、躍進するか否かを賭(か)けた人体進化論(ダーウィン的な適者生存や自然淘汰の進化論ではないので注意)が、更(あらた)めて浮かび上がってくるのです。 つまり霊主体従であり、唯霊に対する唯神論という立場です。 さて、唯神論(唯心論)に発展すると、霊的な存在が、物質界で、ただ存在しているという事だけではなく、ヒエラルキーとしての階統制、あるいは階層制、更には位階制が存在するという事になります。 宇宙は創造主によって存在し、創造主の霊的宇宙が反映されて、その原理が造られ、それが造物主の存在となった、と考えられます。これが唯神論の全貌(ぜんぼう)です。 ところが唯霊論は、唯神論と同様に、霊主体従の立場を取りながらも、その場の創造目的とか、あるいは人間が一種の造物主なのか、それとも何者かに造られた被造物なのか等の問題は発生しません。 これらは宗教の世界によるヒエラルキーの問題であり、唯霊論においては人間が、「神だけが総て」と思うのではなく、存在の基本に創造する神の意志、あるいは造物主の意志が働いているという考え方に至ります。 こうした論理的な発展は、哲学史に多く登場し、差し詰め唯神論を、概念的に捉えようとしたライプニッツ(Gottfried Wilhelm Leibniz/ドイツの数学者・哲学者・神学者。微積分学の形成者。モナド論ないし予定調和の説によって、哲学上・神学上の対立的見解の調停を試みた)のような大哲学者もいます。 モナド論(monadology/単子論) は、ライプニッツ(Gottfried Wilhelm Leibniz/ドイツの数学者・哲学者・神学者で、微積分学の形成者で有名)のモナド(単子)についての形而上学説です。 モナドは発展段階を異にした力や作用を実体化したもので、広がりも形もない単純な分割できない実体で、それが完結した表象体、あるいは表象存在して、これが無数に集まって宇宙を形づくっているとする仮説です。この事から、一番表象力が活発なのが、「神」とする説です。 神になると、表象したら直ぐに存在するのですから、表象と存在が一つであるものを神と定義している分けです。 またモナドの作用は表象作用で、それには明暗の程度があり、暗い表象作用を持つのが物質的なモナドであり、霊魂や理性的精神のモナドは、明るい表象作用を持つが、その明暗の推移は連続的であるとしています。 もっと解り易く言うと、喩(たと)えば地上の世界において、最高に表象力が活発なのが水冷式哺乳動物の形を持つ人間で、その次に人間より表象力の暗い哺乳動物、更にはその他の動物と繋がり、その次に夢のない眠りを続けている存在が植物であり、最後に死んだ人間の死体や動物の死体であり、あるいは鉱物であるというふうに、総て全部を表象して考えていきます。 そしてこのポイントは、夢のない眠りを営んでいる単子と、夢のような表象を営んでいる単子とが、無限に複雑に絡み合って全宇宙を構成していると考える、このヒエラルキーを説明するのが単子論の全貌です。 したがって単子論は、抽象化された唯神論ということにもなります。 更にモナドは、相互作用を欠く閉鎖的実体ですが、各々の明瞭度で宇宙を映し、相互間に予定調和があるとされ、ライプニッツはこの説によって、目的論と機械論との対立を克服し、心身の対応関係を説明した大哲学者でした。 モナド論に立つ思想家の中には、ライプニッツの他に、ジョルダーノ・ブルーノ(Giordano Bruno/ルネサンス期のイタリアの自然哲学者)で、コペルニクスに影響され、宇宙は永遠・不変な唯一の無限的存在を提唱)やゲーテ(Johann Wolfgang von Goethe/ドイツの作家。青年期の抒情詩や戯曲『ゲッツ』、書簡体小説『若きウェルテルの悩み』で疾風怒濤期の代表者)らの人がいました。 |