■ 兵法 ■
(ひょうほう)
●固定観念を持つな
では何故、一刀流で済む稽古に二刀流を用いるのか。
武蔵は二刀流を、大小二刀を以て戦えとは断言していない。ここが隠れた部分である。そしてこの隠れた部分こそが二刀流、即ち二天一流の極意なのだ。
武蔵は自分の実戦を通じて会得したこの流儀の極意を、二刀で戦う事を最高の極意としていない。これはあくまで方便であり、仏教で言えば念仏宗の「俗諦」と、法華経の「真諦」くらいの差があるのである。
武蔵の名付けた「五輪」には仏道の五輪が用いられ、五行説が加味されている。
『五輪書』を解釈する見識の低い者は、その五輪の「陰陽五行説」ばかりに眼を奪われ、その奥に隠された「真諦」(しんてい/真理)に当たる部分を見逃し、安易にも「俗諦」(ぞくてい/方便)のみを取り上げて、愚かも、これを有難がっている剣道愛好者が多い。
では『五輪書』の言う「真諦」とは何か。
武蔵は陰陽五行を揚げ、仏道の「五輪塔」に準(なぞら)えて、五大(ごだい)をかたどった五つの部分から成る塔を模したものである。
五輪塔は下から順に、地輪は方、水輪は球、火輪は三角、風輪は半球、空輪は宝珠形とし、これは平安中期頃から供養塔あるいは墓塔として用いた塔である。別名、「五輪卒塔婆(ごりんそとば)」とも言う。
即ち、「地・水・火・風・空」を著わし、五行を循環されれば、「火・木・土・金・水」を著わしているが、要は「変応自在」が真諦の主体であり、「火は大きくもなり、小さくもなり……」とあるように、その人間の心の在り方を戦闘に準えているだけの事なのである。その言葉尻だけを捉えると『五輪書』は、単に精神訓になり、実践する実践者の真諦とはなり難い。
武蔵の言う、「一切の迷いを断ち切った心境」とは、「人間が最大限の修練を積み重ねる事で、人知の及ぶべき次元を超越せよ」と言っているのである。
つまり「常識の範囲で物を捉えるな」という事だった。
だから「二刀流なのだ」と、実証的帰納法に回帰すれば、この命題は自ずと答えが出てくるのである。
武蔵の言う「常識」は、世間一般の凡夫の「神佛に願を賭ける心」や、並の剣士の「一刀流にこだわる心」であり、要約すれば「こだわるな」という世間風の常識が、人間を弱くすると言っているのである。
「こだわり」が、ジレンマを招き、六道を輪廻して、災いをもたらすともいうのである。
だからここから解脱する為には「空」の心境が必要で、「人知の及ぶべからず境地をする事が、解脱イコール空なのだ」を言っているのである。
兵法の知恵、兵法の道理、兵法の精神はこうした空の境地のものであり、「一切のこだわり」から離れて、はじめて物事の存在しない世界に至れ、と解釈できるのである。
その為に武蔵は、難解で複雑な「二刀流」を選び、この二刀流の中に極意があるとしたのである
●兵法としての二刀流の極意
一刀流は左右両方の手で、一振りの刀を遣う。その左右は五分と五分の、我が両手に委ねられる。五分と五分を合わせて「十分」とするならば、やはり左右に分ければ五分と五分である。
しかし武蔵はこの鍛練法として、一振りの刀を、左右両方の手に握って、五分と五分の合わせた十分を、それぞれ左右に、十分の働きを負わせる事が出来ないかと考えたのである。
ここが武蔵の天才たる所以である。
武蔵の考えは、左右に五分と五分を分解して、五分を「一」とし、一から練り上げてやがて「十」にまでその能力を高める。十に高まった左右は、合わせれば「二十」である。二十が十に負けるはずがないのだ。これが兵法の道理である。
しかしこうした鍛練法は一般向きではない。そこに二天一流の難解な箇所が存在するのである。
したがって天才武蔵は、剣術指南として、その難解故に、何処の藩でも用いられる事はなかった。
武蔵に悲劇があるとするならば、こうした点であり、有能な武士と認められるよりも、一流の武芸者の範囲を出て評価されなかった事であろう。
それは評する者の固定観念が働いている為である。
武蔵は固定観念の愚を説いている。
喩えば、太刀の持ち方一つにしても、他の剣術の考え方とは異なる。
また動きにしても、固定してしまってはならないと説く。固定観念は死であり、固定せぬ事が生であると教える。
物事は変化し、流転し、発展し、進化するところに価値がある。
これは個人も企業も、そして国家でも同様である。これらが進歩を止めた時、それは崩壊する。流れる水は腐らない。水が止まり、淀めばやがては腐る。こうした事を「水の巻」に述べている。
●帝王学は一般向きではない
現実を見れば、人間の要素は裏と表を持ち合わせる。表面は形に見えるが裏面は形に見えない。これが陰と陽の関係である。陰陽極まりて無が有になり、そしてやがては有が無に帰る。
その繰り返しは歴史の中でも存在している。
最初、時代を動かしていたのは上層階級や、それを掌握する天子に限られていた。
ところが時代が下がるにつれ、時代とともに、その動かす原動力も下へと下がることになる。
その最も良い例が、戦国時代の「下剋上」であろう。
この時代、人々は誰から賄賂を貰おうと、女を犯そうと、お稚児(ちご)と寝ろうと、主人を殺そうと尤(つが)められるものは何一つなかった。したがって思う存分、振る舞う事が出来た。
織田信長にしても、天皇を利用したけれども、あるいは足利将軍の威光を被ったけれども、信長にとってこれらの権威は大したものではなく、男色に耽ることすら悪の対象ではなかった。
それはこの時代、キリスト教に当たる律法がなく、また中国からは儒家の思想が輸入はされていたが、それほど一般には浸透せず、さしたる道徳訓も存在しなかった。
だからこそ、個性の強い信長は、自由に、勝手気儘に振る舞い、その個性から、歴史を動かす原動力が弾けたというべきであろう。
古代ギリシャにおいても、次々に哲学者が、自由に、徹底的に思考を追求する事が出来たのは、一つには支配的な大哲学がなかった為である。したがってこうした中では、自由闊達な者が、多角的な価値観を需(もと)めて、あらゆる専門分野を伸ばす事が出来た。
ところがキリスト教が律法を定め、善悪二元論ができ上がると、人々の思考は狭くなっていく。今日でも哲学が、プラトン以上の次元を超えられないのはこうした事からである。
人は自由を需めて旅をするというが、果たしてその自由は、かつての封建時代より、今の方が自由といえるか。
否、一見現代の方が自由に見えながら、実は徳川封建時代よりも更に不自由な時代になっているのである。
長い歴史の集積や、文化の集積から来る不自由さは、複雑な経路を辿って、今日に至り、敗戦と占領によって生み出された民主主義と国際主義は、否定はおろか、批判すらできない様々な不自由さが絡み付いている。
少しでも本音を漏らし、本心を言うと、忽ち袋叩きにあう。
人は建前だけを表面に出し、肚(はら)では腹芸として、本音の探り合いをする。
それは韓非の時代と変わらない。あるいはもっと不自由であるかもしれない。
韓非は言う。
「人が、他人の落し物を拾わず、あるいは着服せず、商人は掛け値でなく、正価で物を売るようになったのは、孔子の徳に服したからではない。人々は、孔子が法家の術を遣って、不正を働いた大臣を処刑するのを見て震え上がり、自分も孔子の言う事を聞かなければ殺されると思って、孔子の命令に従っているまでのことである」
韓非の言は、まさに本音であった。
したがって政治家がこの本音の道に従い、政治を行えば、何ら偽る事はないのである。
こうして考えてくると、『韓非子』は政治家や経営者の道を率直に述べたものとなる。
もっとも、政治家や経営者の中で、孔子や孟子の道を自己の反省材料として用いれば、行き過ぎる箇所にはブレーキとして働くであろうし、エンジンを動かす為には、韓非子の道がその動力となるであろう。
両者は対(つい)として遣ってこそ、初めて役に立つものであって、ブレーキだけが大きくかかって居たのでは、車は前に進む事が出来ない。
政治家は建前だけの政治をし、本音の政治が出来ないから、国民の不幸は益々大きくなるばかりなのである。これは元米国カーター大統領の馬鹿正直な政治が、アフガン進攻を許したという例から見ても分かる通りである。
また無能な経営者は、孔子や孟子を持ち出して、叱咤激励をするから説教調になり過ぎて、「お客様は神様だ」とか、「真心をもって客と接し、感謝しろ」等と、意味不明な難問を社員に突きつける事になるのである。
こうした会社の経営者に限って、自分の建前の言葉とは裏腹に、物財で取り巻かれた生活をし、妾を何人も侍(はべ)らせて、会社の経理を火の車にしているのである。
こうした例は幾らでもあり、元東京都知事の美濃部知事は都内で行われる公営ギャンブルを廃止し、福祉のバラ蒔きをやったお陰で、官僚だけが良い思いをするという構造ができ上がり、都民は何ら利益を受ける事はなかった。むしろ東京都の財政を悪化させて、破綻寸前まで追い込んだのは、この政策を打ち出した美濃部都知事自身であった。
政治家が孔孟の道を取った場合、本音を隠す為に偽善者となり、表面だけを繕った、欺瞞(ぎまん)の輩(やから)で、政治は動かされる事になる。だから韓非子流の本音の政治が必要になる。
しかしこれは、こうした者に限られる事であって、指導者たるべきものは、韓非子流は必要であるが、大衆は、むしろ韓非子流で行くよりは、老子流(宇宙の本体を大または道といい、現象界のものは相対的で、道は絶対的であるとし、清静・恬淡(てんたん)・無為・自然に帰すれば乱離なしと説く思想)で行く方が、より一層幸福になれるかもしれない。大衆は、帝王学など無用なのだ。
つまり兵法とは、有用と無用を選別し、適材適所に、誰にこれを配布するかにある。
兵法指導者に、こうした見識と洞察力がなければ、その指導は誤った事になる。
●為(な)すが儘(まま)という無為の思想
以上、兵法を述べる上で法家の理論を述べてきた。
しかし西郷派大東流合気武術は、『韓非子』あるいは『管子』とも、少し違った兵法哲学ならびに人間論を持っている。この論理こそ、我が流派で言う「武士道」である。
例えば韓非は、「君主が賢明だと解れば、人々はそれに応じて用心し、君主が暗愚(あんぐ)であると解れば、人々は君主を騙しに掛かる。また君主が無欲であると見れば、人々はその実情を探り、欲があると見れば、人々は君主に欲を餌にして誘き出そうとする」と述べている。
それが「無為」を最上とする韓非の説である。
この説の件(くだり)には、「お前は言葉を慎め。人はその言葉によって、お前を知ろうとするだろう。お前の行動を慎め。人はその行動によって、お前に尾を振ってくるだろう。また、お前に知恵のある事が解れば、人はお前になにも言わないであろう。更に、お前が無智である事が解れば、人はお前を欺こうとするであろう」と言い捨て、「人の窺(うかが)えるのは、無為だけである」と一蹴している。
だから韓非は、「他人から見れずに、己だけが見るのを『明』と言い、他人から聞かれずに、己だけが他人の言を聞くのを『聡』という」という「明と聡」を証し、「己だけで判断する者は、天下の主になる事が出来る」としているのである。
ここに庶民大衆の、おおよそ考える、総ての打算が集約されていると言っても過言ではないであろう。
そして日本では、天下取りにその飽くなき念を燃やしたのが、織田信長であり、その後を受け継いだ豊臣秀吉であり、徳川家康ではなかったか。
しかし西郷派大東流武士道集団は、こうした「悲愍(ふびん)なる人間」を超越して、一方で韓非子や管子を認めつつも、単に現実逃避を企てるのではなく、現実を瞶(みつ)めながら、人民に奉仕するには、単に欲望の絡む次元を離れて「仁」を全うする事が出来ないかという思想を展開している。
それが為(な)すが儘という「無為の思想」である。
●為すが儘
為すが儘とは、「こだわり」を捨てるという事である。
つまり武術の哲学は、同時に「虚」の哲学でもある分けだ。
こだわりを捨てるとは、自由自在に動く事であり、制約や制限を超越する事である。
合気武術の奥儀は、「合気」に代表される分けであるが、合気とは「やわら」であり、自由自在の動きを指すのである。
この真境こそが、
風なりに春は雨降る柳かな
であり、柳は風のままに東西南北と、いずれの風にも揺れ動き、風のままに流れ、決して風に逆らおうとしない。つまりここには「虚」の行動原理があるのである。
これはまた、兵法も同じである。
兵法は、単に試合に勝つ為の個人決勝戦を競うものではない。
全体を見ながら、陣取り合戦を行うのが兵法であり、戦いの局面を知恵で、弄(ろう)せずして、手に入れるのが兵法の極意である。
更に追言すれば、ただ努力して自分の力を使って、実力通りに力み、意志通りに敵を動かすというものでもない。そんな事をしていたら結局、戦う前に自滅してしまうのである。
ここに、肩が凝る、疲れるという不吉な運命が待ち構えているのである。
戦いにおいて、敵が自分の意志通りに動かぬから、こちらが崩れる。また、わが力で、われを倒すような事になりかねない。こうすると先方の動きに合わせて、こちらが自在に変化する能力を失うからである。
「やわら」とは、敵の動きに合わせて「変転」する事をいう。
その変転の基本理念と哲学は、「為すが儘」なのである。
例えば、腕でも、足でも取られたら、そのままにしておき、そこを捨ててしまう事なのである。そして別の局面から勝機を掴む事を主眼とするのが「為すが儘」の精神である。
しかしこうした兵法理論に慣れないと、大方は、取られた処を取り返そうとして、更にその損失を大きくしてしまうのである。
また碁や将棋の世界には、「死棋腹中、勝機あり」という言葉がある。
碁や将棋において、へたな一手を打って、その局面が危うくなると、それを盛り返そうとして、更にアレコレと次の手を打ち、結局その小細工が命取りになって大敗を喫してしまう事が少なくない。
人間は、概ねがこうした精神的な心の作用で支配されているが、何故このような作用に支配されるかというと、損したところ、取られたところ、失った箇所が眼に入り、失ったこと事態を「惜しい」と思うからである。結局「取り返そう」「失うまい」と言った心の虚を、逆につかれて、結局は全体を失ってしまうのである。
人間の生活や、その心情による行動原則は、概ねが「やられたら、やりかえす」という事が原則になっているようであるが、これは一種の心の錯覚である。
損したと映るだけである。
したがって、へまをやった処を取り返そうと焦るには及ばないのである。放って置けばよいのである。捨ててしまうという現実にこそ、人生最大のテーマがあるのである。
そのテーマは、惜しいと思うよりは捨ててしまって、前を見る、先を見るという事が肝腎なのだ。これを「見通し」という。
結局、見通しの立たない人間は、『韓非子』や『管子』の確言すら掴めず、墓穴を掘って自滅する運命にある。
●運命を抜ける術
損に引っかかり、失った処に引っかかるのは「抜ける術」を知らないからである。
小人(しょうにん)は益徳に転び易い。
その人が、小人であるか、否かは、運命を抜ける術を知るか、否かに掛かっている。
運命は左右できないものである。
如何なる戦いにおいても、人間の力で勝負を左右する事は出来ないのである。戦いは、勝にせよ、負けるにせよ、実のところは「逢って、抜ける」だけの事である。
したがって運命からは逃げ出す事が出来ない。それを迎かえ撃って、それを果たして行くものなのである。損をしたら、損をしたままに放っておく。これが因縁に「順」なるところである。
これは恰度、貧乏が嫌といって逃げ回り、益々貧乏になって行くのと酷似している。
したがって貧乏からはいつまで経っても離れる事ができないのである。
「恐れるもの皆来る」の諺はこれに由来する。
貧乏から逃れようと、貧乏に脊(せ)を向けて、いつまでも逃げ回っているから、貧乏を生涯背負って行かなければならない事になるのである。
反対に、頭を貧乏の方に向け、貧乏の中に突入して行けば、貧乏と私は一体になり、この一体になった時に初めて、貧乏が貧乏でなくなるのである。貧乏から逃れようと企てれば、貧乏と私は常に二つになり、貧乏に心を奪われて全局面を、全生涯を失うのである。
戦いは、まさにこれと酷似しているのである。
●同じ戦場でも、攻略の考え方は三つある
攻略の考え方として、敵より我が勢力が勝(まさ)っていれば正面から正攻法をとる。これは凡将といえども、在り来りの攻略法である。
問題は、敵の勢力より、我が方が劣っている場合である。
この場合、遊撃戦(ゲリラ戦)に出て、迂回すると見せかけて、実は側に着いたり、背に廻り込む事を考える。そして次の問題が起こる。
それは右に廻り込むか、左に廻り込むかである。右に廻り込む事を右旋といい、左に廻り込む事を左旋という。単に側面や背後から襲い、蹴散らすだけならば、右旋が有効であるが、最後の掃討まで考え、敵の大将の馘(くび)を挙げるのならば、左旋が有効であるが、それだけに危険も多い。
その場その場の、将たる人間の決断と実行に委ねられる。
勢力が敵の二倍に匹敵し、正攻法がとれるのであればこの方法が、間違いなく有効である事は凡将でもはじき出せる。
しかし逆に、敵が我が方の二倍以上、あるいは十分の一程度であるならば、正攻法をとれば全滅する事は疑いの余地もない。
したがって戦いは正攻法以外の、遊撃戦に頼らなければならなくなる。
孫子の兵法の基本は、かつて毛沢東が、解り易く部下に説明した通り、「一を以て十に当たり、十を以て一に当たる」という事であり、敵が多勢であれば側面に密着しつつ、ゲリラ戦で悩まし、敵が劣勢であれば、一気に敵の勢力の十倍の数を以て、正攻法に打って出て、一気に勝敗を決するのである。これを局面的に繰り返せば、今は全体が劣勢であっても、局面戦争でこれを繰り返すのであるから、やがて「勝機」が生まれるとする戦略思想である。
| |
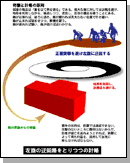 |
|
 |
|
 |
▲攻略の考え方
左旋・正面・右旋(クリックで拡大) |
さて、策略の本来の意味は「敵を騙す」ことではない。人間の心理に流れている、その流れを見抜いて、戦法の効果をシュミレーションして、無理なく勝機を掴む事である。
そして如何なる戦いも、条件が変われば、当然その答えは違ってくるのである。
また一を以て十に当たり、十を以て一に当たる、という毛沢東の確言は、孫子の謂(い)う「我専(あつま)りて一と為(な)り、敵分かれて十と為らば、是(これ)十を以てその一を攻むるなり」という孫子兵法の、敵の戦力を分散し、その一部のみを徹底的に攻めよという戦術理論に立脚するものである。
「人を形(かたち)せしめて、我れに形無ければ、則ち我れは専まりて敵を分ける」
孫子兵法の基本理念は「人を形せしめる」であり、この思想は、敵にはっきりと眼に見える態勢をとらせる事で、ある意味で敵の、様子が手に取るような状態を作る事にある。そして逆に、こちらは「形無し」の態勢を作り、敵側に分からせないという、敵側から見る疑心暗鬼である。
敵はこれによって、こちらの小勢力を防ぐのに、大軍を繰り出して防ごうとするし、大軍を繰り出せば、その局面の陣地は手薄となる。そこでこちらは、密かに十の力を一つに集め、十倍の力を以て、敵の一を叩くのである。
こうした戦術思想は、戦闘において主導権を取り、兵力を集中させる事によって、敵の優勢な陣地を崩すのに役に立つのである。
しかしこうした戦いの裏側には、やはり『韓非子』の法家の理論が働く事は、紛れもない事実である。
●戦国時代に例えられる現代の企業間の経営者像
現代は乱世の戦国時代に例えられる。デフレ不況の荒れ狂う今日、世の中は混沌として、一種の風雲急を告げているように思える。
したがって多くの経営者が研究する参考資料は、圧倒的に戦国期の故事ばかりが多い。しかしこうした故事も、多くは戦術や闘い方ばかりを研究して、根本的な人間観までには迫っていない場合が少なくない。
多くは戦術としての、自己啓発法であったり、社員の修養法であったりして、その低い次元で止まっている。
社長が陣頭指揮を取り、朝礼で大声を張り上げ、社員を叱咤激励する。これは決して悪い事ではない。しかしこれだけで社員を動かし、これまでの売り上げが二倍に増える分けではない。
無能な経営者ほど朝礼で大声を張り上げ、また社員にもこれを押し付けて肉体派の営業を展開しているが、こうした側面のみを守っていれば、売り上げは倍増すると考えるのは早計である。
まして経営者が孔子流の『論語』を持ち出して、いっぱしの孔子論を垂れた場合、事は最悪となる。自分では良いことを言っているような錯覚に陥っても、あまりの建前の矢継早で、しらけてしまうからだ。
無能な経営者は「お客様は神様です」などと、心にありもしない事を言う。「感謝」という言葉を連発する。しかしこうした経営者ほど、「お客様を神様と思わず」本音では「感謝」など、心の裡では毛頭ない。
「有難う御座います、○○株式会社でございます」等という中小企業は、既に斜陽に差し掛かった会社であり、外交辞令を形式的に、惰性でやっているに過ぎない。斜陽に差し掛かった会社と、高利貸し企業は、二枚舌で顧客予備軍を「有り難うございます」の、孔子流の言で繕おうとするのである。
さて、世の中には絶対真理が「三つ」ある。
その一つは、人間は、知力を総結集しても成し遂げられない事がある。その二つは、幾ら大力の持ち主でも、持ち上げられないものがある。その三つは幾ら最強を自称しても絶対に勝てないものがある。
これに準えて、韓非は『韓非子』の中で、
「堯(ぎょう/堯・舜に例えられ、優れた天子の意)ほどの知があっても、衆人の助けを借りなければ大功は立てられないし、烏獲(うかく/秦の武王の時代の力士)ほどの力があっても、衆人の力を借りなければ自分の躰(からだ)を自分で持ち上げる事は出来ないし、孟賁(もうほん)・夏育(かいく)ほどの強健な者でも、方法と手段と秘策がなければ、いつまでも勝ち続ける事は出来ない。だから情勢ではどうしようもない事があり、物事の道理上、どうしてもやりとげられない事がある。
したがって烏獲が千鈞(せんきん)の物を軽く扱う事が出来ても、自分の躰を持ち上げられないのは、その躰が千鈞より重い訳でなく、情勢が兇(わる)いので持ち上げられないのである。離朱(りしゅ)は、百歩向こうにある物を鮮明に見る事が出来るが、自分の眉や睫(まつげ)を視る事が出来ないのは、百歩が近くて眉や睫が遠い訳でなく、物事の道理上、それが不可能であるからだ。だから明君は、烏獲に向かって、なぜ自分の躰が持ち上げられないのかといって責め立てたり、離朱に向かって、なぜ自分の眉や睫を視る事が出来ないのかと尤めたりせず、有利な情勢によって、やりやすい方を求める。だから、明君の下では、労少なくして功名を立てるのである」
(観行篇)
とある。
韓非は君主の中にも、無能な者と有能な者が居る事を述べている。無能な君主に下に居ると、一生冷や飯食いだが、有能な君主の下に就くと、道理を承知していて、建前だけの心にもない事を言ったり、それを強制しないものだとしているのである。
●栄枯盛衰と運・不運
現世の現象は変化であり、それは刻々と変化する。したがってその変化は、無が有になり、有が無に帰る変化であるし、陰から陽に変化し、再び陰に戻るという変化である。
これを古人は「栄枯盛衰」と言った。
時運には、熟している時とそうでない時があり、物事には利のある時と害になる時がある。そして事象は盛衰である。
韓非はこうした現象を鋭い観察力で捉え、明君を診断した。
「君主が人間の表皮を飾る、稽古盛衰と喜怒哀楽の色を表わすと、金石のように堅い心を持っている臣の心も、君主から離れ、聖賢の徒も、君主の思慮のあるなしを見抜いてしまうだろう。
したがって明君は、人を能く観察して、人に自分を観察させないようにしなければならない。
堯でも一人では何も出来ず、烏獲も自分の躰は持ち上げる事が出来ず、孟賁でも自力では勝てない事を心得て、法術を用いれば、家臣の行為を観察する方法は万全である」
つまり韓非は、人間のする事に「順風満帆」はあり得ないとしているのであり、また、人の一生も、順風満帆はあり得ないとしているのである。
人間修行の場は「変化」なのだと力説する。
「堯・舜が生まれながらにして天子の位にあるように定められているのなら、桀(けつ/夏(か)の最後の君主で、名は履癸(りき)、桀はその称号。殷の湯王に討たれ、山西省安邑県の北の鳴条に走って死んだという。桀王)・紂(ちゅう/暴君の典型として殷の紂王。湯王とも)が十人現われても世を乱す事が出来ない。そのように自然は定まっているのだ。
反対に、桀・紂が生まれながらにして上に立つように定められているなら、堯・舜が十人現われても天下は治める事は出来ない。ただそれだけで、自然の勢いは乱れるようになったいないからだ。
勢が治まるようになっている時には乱れようがないし、勢が乱れるようになっている時には治まりようがないのだ。
それは自然の勢であって、人間の力で設けられているのではない。こうして論ずる『勢』は、人間が設ける事のできる勢であって、人間の『賢』など、無用なのだ。(【註】「賢」とは、儒家の聖賢を指す)
韓非は流転する現世に、一つの法則を認めた。栄枯盛衰も如何ともし難く、また運・不運も如何ともし難いものであるが、人間の設ける「勢」は、それを自動制御する事によって、組織を動かす法として働き、それを動かすのが管理という「術」なのだと説くのである。
韓非は「賢」と「勢」は両立しないとして、有名な「矛盾」という用語をつくり出した人物である。
●法・術・勢
韓非が集大成をした『韓非子』は、基本的には三つの要素から成り立っている。これが「法・術・勢」である。
法とは、儒家の礼治に対抗した法治の提唱であり、術は厳刑峻法を以て、民を治める手段であり、戦争を中心とする富国強兵であり、また勢は君主先制と、郡県制を基礎とした官僚制による中央集権制度を目指した政治論であり、過去より現在を最優先する発展的歴史観と唯物的な性悪説の拡大である。
これを総じて、東洋のMachiavellismとも言われている。
韓非の生きた時代は、春秋時代から戦国時代にかけてであり、これまで周王朝が諸侯を支配していた封建制度が揺らぎ始め、弱肉強食の時代になり、家柄より人間の能力が優先されて、下剋上の風潮が広がり始める頃だった。
そしてこうした現実下では到底「仁義」など存在し無い現実があった。
この韓非と同時代の政治学説を説いたものが『管子』であった。
『管子』の著者は管仲(秋時代、斉の賢相。法家の祖。名は夷吾。字は仲・敬仲。河南潁上の人。〜前645)で、彼は親友鮑叔牙(ほうしゆくがのすすめ)によって桓公に仕え、覇を成さしめた。『管子』はその名に託した後世の書である。
一般には、管鮑(かんぽう)の交まじわりで有名であり、『史記管仲伝』には、管仲と鮑叔牙とが互いに親しくして、終始交情を温めた事から、 友人同士の親密な交際を指す言葉として用いられる。
この中に管仲は「与える事が取れる事になる。これを知るのが政治の要締である」と言っている。
『管子』には、例えば「法を法とせざるときは事(こと)常になし」あるいは「聖君は法に任せて知に任せず」等の言葉があり、法を論じた篇が幾つも出てくる。
そして極め付けの締め括りは「総て人間の遣る事は、名誉の為でなければ、利益の為である」と断言している。
『管子』の冒頭には、「倉廩(倉の中の品物)実(み)ちて則(すなわ)ち礼節を知り、衣食足って則ち栄辱(えいじょく)を知る」との件(くだり)がある。
この言葉は、精神主義偏重を戒めた非常に興味深い言葉である。そして以降法家は、この考え方で時代に示唆を与えていく。しかし『管子』と言う書物は、顕蜜に言うと、秋時代ではなく、実際には戦国時代から前漢食に書かれた書物であると言われている。
●『韓非子』を知らなかった明智光秀
織田信長の天下取りを演出した功労者は、何といっても明智光秀である。
しかし光秀といえば、戦国期の最大の謀叛人としての悪評が高い。知性があり、インテリタイプで、陰険なイメージを誰でも連想されよう。
しかし果たしてそうであったのか。
確かに光秀は教養深く、冷静で、洞察力や観察力も深かったようだ。しかし苦労知らずの家柄に固執して育った、やわな人間ではなかった。
彼の運命は、不遇と貧乏の連続であった。四十歳過ぎまで諸国を渡り歩き、兵法修行を重ねながら、自らを励まし、漂泊の人生を送った努力の人である。
ところが、こうした光秀にも立身出世のチャンスが巡ってくる。
それは足利義昭(よしあき)が、光秀を信長に引き合わせる事から始まったのである。光秀にとっては絶好の大チャンスであった。
当時、足利幕府が存在していたが、将軍職の権威は地に落ちていた。
永禄八年(1565)、足利十三代将軍義輝が、三好一族とその被官の松永秀久との共同某議によって殺害された。それに代わって十四代将軍義栄(よしひで)が将軍の座に就いた。しかしこれは傀儡将軍であった。
「こうした破廉恥な下剋上が許されていいものか!」
こう、憤懣やる方ない怒号を発したのが、義輝の弟・義昭であった。
義輝は奈良興福寺一乗院の門跡におさまって、世捨人の姿を送っていたが、兄・義輝が殺されると壮挙して、全国の諸大名に庇護と支援を呼びかけた。
しかし義昭の呼びかけには誰も応える者がなく、厄介者扱いされて全国を流浪した。そして流れ流れて辿り着いた所が越前の朝倉義景であった。
しかし義景も、義昭の来訪はありがた迷惑であり、日夜歓待はしたが、武力援助までには至らなかった。義昭は途方に暮れた。
この流浪の将軍血縁に随従していたのが、有名無実の管領家・細川藤孝(ふじたか)であった。
藤孝は後の幽斉であり、忠興(ただおき)の父である。教養が深く、文武両道の武士として知られていた。
こうした藤孝と因縁を結んでいたのが光秀であった。光秀は当時、朝倉家の食客となっていたのである。
ある日、藤孝は光秀に嘆いた。
「御当家は、われわれに良くはしてくれるが、肝心の逆賊討伐の武力援助をやってくれない。これではいつまでたっても幕府再興の夢はかなえられぬ」
この言葉に光秀は閃(ひらめ)くものがあった。
「ならば、織田家の頼んでは如何ですか」
藤孝は、桶狭間で今川義元を破った信長の武勇は承知していたが、織田家は新興勢力であり、信長の粗暴の噂に一瞬危ぶんだ。
「さに非(あら)ず!」光秀は一喝した。
光秀は、信長の真の隠された性格、行動力、決断力、判断力、そして類まれなるその気性を詳しく説明した。そして信長によって新しい世の中が開かれる事を力説した。
光秀の父・明智光綱の妹が斎藤道三の後妻に入り、生まれた娘が帰蝶(きちょう)であった。帰蝶が信長に嫁したというのである。となれば、光秀と帰蝶は従姉弟(いとこ)同士になり、信長とも縁があるのである。
こうした話に義昭は強い関心を示し、一切を藤孝と光秀に託した。
こうして信長と光秀の縁が結ばれていく。
「将軍のご意向」という大義名分を以て、信長の畿内征服は順調に進み、光秀は信長の「知恵袋」として活躍していた。
また光秀は、将軍義昭と信長の双方からの依頼で、その任務に当たった。弁説爽やかで、文武両道に通じた兵法家・光秀には打って付けの仕事であった。得意絶頂期であった事は疑う余地がない。
光秀は、魚が水を得たように生き生きと働いた。
公家の調停、儀式の設営、内裏の修理、禁裏御料の確保、公卿領や寺社領の訴訟事の始末など……その働きは目覚ましいものであった。そして多くは京都に在住した。
また信長が京都にやってくると、彼は光秀邸を宿舎とした。
高度成長期の信長にとって、光秀は宝同様の人材であった。したがって信長の、光秀に対する扱は丁重そのものであり、厚遇を以て光秀を遇した。
信長に仕えて三年目、光秀は近江国滋賀郡に坂本城(大津市)が与えられ、十万石の大名に遇ぜられた。時に光秀四十四歳であった。
子飼いの信長の重臣である羽柴秀吉でも二万石の長浜城主になったのは、信長に仕えて十五年目の事であり、それから考えると、光秀は異例の大出世であった。
しかし光秀に、信長のこうした真意は見抜けなかった。
信長は飛ぶ鳥を隕(おと)す、高度成長を遂げる破竹の勢いを持った名将であったが、所詮、その中味は独断専行の独裁者であった。
光秀はこうした信長の正体を見破る事が出来ず、信長との蜜月は永遠に続くものと錯覚していたのである。
信長は、異常に自我が強い、一種の野人である。また性格は、光秀とは正反対であった。
ある発展途上時期に、こうした正反対同士の者は、時機として水魚の交わりとしてぴったりいくが、ある程度の成長を遂げた段階では、逆に衝突が免れなくなる。
やがて「能力はあるが、虫のすかぬ奴」というふうになり、両者の葛藤は眼につくものになり、これは漢帝国初代皇帝の劉邦(りゅうほう)と韓信(かんしん)の仲を見ても一目瞭然である。
韓信は漢初の武将であり、蕭何(しようか)・張良(ちょうりょう)とともに、漢の三傑といわれる人物である。
高祖・劉邦に従い、蕭何の知遇を得て大将軍に進み、趙・魏・燕・斉を滅ぼし、項羽を孤立させて天下を定め、楚王に封、後に淮陰侯におとされた。しかし劉邦の嫉妬から、謀叛の嫌疑で誅殺される。
青年時代は辱しめられ股をくぐらせられたが、よく忍耐した事は「韓信の股くぐり」として有名である。しかしこれだけの武将でも、嫉妬から誅殺されるのである。
韓信が誅殺された時、蕭何は賢明であった。
蕭何は前漢の宰相で、江蘇沛県の人であり、劉邦と知り合った時は田舎の小役人に過ぎなかった。しかし劉邦の人物に惹かれ、以後高祖と崇め、彼とは一線を引いて尊んだ。やがて劉邦を皇帝にまで押し上げる。
関中に入るや秦の律令・図書を収め、軍政・民政に通じ、劉邦が項羽と争った時、よく関中の経営にあたり、後顧の患をなくした。そして一時は漢の宰相にまで登り詰めたが、韓信が誅殺されると、今度は自分の番とばかりに、即座に宰相を辞め、僅かな田畑をもらって田舎に引っ込んだ。
まさに『韓非子』を熟知していたといえる。
しかし光秀はこうした教訓に眼を向けなかった。
「敵は本能寺にあり」の号令を発して、光秀は謀反を決意する。その後、光秀の末路は周知の通りである。
光秀と秀吉が雌雄を決したのは「山崎の戦い」である。
この戦いは僅か数時間で決着がつき、光秀軍は敗走した。光秀は再起を計るべく、僅か五、六騎で居城の近江坂本に向かったが、途中の小栗栖(おぐるす)の竹薮で、武者狩りの土民に竹槍で脇腹を刺され、そのまま駆け抜けて、三町ほど行った所の村外れで落馬し、絶命したといわれる。
一般には、明智光秀は「三日天下」と言われて、謀叛の大悪人として評価されているが、実際には十一日間の天下取りであった。
|





